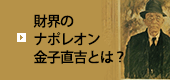羽幌炭砿のあゆみ ~Ⅲ.戦後の混乱期(昭和20年~25年)~
終戦後の幾多の困難を乗り越え、合理化のスタート ラインにつく
太平洋戦争は昭和20(1945)年に終戦を迎えたが、日本の国土は惨状を呈し、社会全体が大混乱に陥った。昭和21(1946)年、政府は「傾斜配分方式」を決定し、戦後経済再建の突破口を石炭、鉄鋼、肥料の集中生産に求め、特に石炭は国の最重点産業とされ、緊急の増産対策が講じられることとなった。
羽幌炭砿も人手・資材・食料不足、労働意欲の低下に加えて乱掘により荒廃した坑内での自然発火の頻発などにより、さらに、終戦と同時に発生した朝鮮人労働者の蜂起がヤマの荒廃に拍車をかけ、昭和20年度の出炭量は4.8万㌧余りと前年度の半分程度に減少した。このような状況下において、羽幌炭砿は昭和21(1946)年に政府から新規炭鉱開発の要請を受け、羽幌本坑、上羽幌坑の開発に着手するとともに、総力を結集して炭砿の復興にあたった。
昭和22(1947)年には採炭方法を「残柱式採炭法」から「長壁式採炭法」(ロング採炭法)に切り替え、増産体制を築き始める。そんな中、年産800万トンを誇る満州の撫順炭鉱で採炭の第一線に立ち、最先端技術を有していた朝比奈敬三(後・専務取締役)が迎えられた。この時点で、年産100万トンに向ってスタートが切られたといってもいい だろう。
昭和22(1947)年8月には上羽幌坑が、翌昭和23(1948)年8月には羽幌本坑が開坑し、この年から築別、羽幌両砿業所の増産を主眼とした第一次五カ年計画がスタートした。
昭和22(1947)年、配炭公団法と臨時石炭鉱業管理法が公布され、石炭の一手買入・販売権が「日本石炭」から配炭公団に移行。炭鉱は国家の管理化に置かれ、保護される形となった。しかし、石炭産業を取り巻く環境は昭和24(1949)年に発表された日本経済の自立と安定を企図した「ドッジ・ライン」により一変する。同年、配炭公団が廃止され、全国の石炭企業は市場での自由競争に突入したのである。
上羽幌坑、羽幌本坑の開発に多額の設備資金を必要としていた会社はドッジ旋風のあおりをまともに受け、借入れが困難になるとともに、政府の援助も半減した。この状況を打開するため、町田専務(後・第二代社長)が上京し長期間交渉にあたるも約1年もの間融資が決定せず、昭和25(1950)年頃まで資材等の支払いができず、一時は閉山を覚悟するほどの状況に陥った。巷では「いろはを忘れたぼろ炭砿」と揶揄されるほどで、この頃が羽幌炭砿にとって終戦直前に次ぐ大試練であった。
この頃、羽幌炭鉱にとって一大危機であるとともに、その後の発展の大きな原動力ともなる事件が起こる。戦後間もなく、全国の産業において労働組合が結成されたものの、その活動は次第に共産党の指導色が濃くなり、築別炭砿の組合活動も次第に先鋭化していった。その結果、築別炭砿において昭和25(1950)年9月から無期限ストに突入し、威力業務妨害の容疑で司法権が発動される事態が発生したのである。
この一大争議を機に会社と組合は共存共栄の道を歩みはじめ、その後羽幌炭砿では1回のストもなく労使協調し、徹底した合理化・技術革新を推進。全国に「中小炭鉱の雄」の名を知らしめることになる。その意味で、このスト終結が羽幌炭砿の一大転転換機になったといってもいいだろう。
昭和25(1950)年、朝鮮戦争が勃発。特需により石炭ブームが到来し、羽幌炭砿の出炭量も上昇カーブを描き出す。