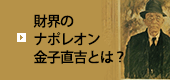鈴木商店の製粉事業への進出②
鈴木商店は札幌製粉の買収、大里製粉所の設立により本格的に製粉事業に進出
明治30年代後半から明治末頃までの時期は食生活の向上に伴う小麦粉需要の増大に加え、政府の積極的な産業振興策が相まって、大資本による製粉会社の新設(*)が相次ぐ一方、既存の製粉会社も規模を拡大していった。
(*)明治38(1905)年頃からわずか数年の間に明治製粉、帝国製粉、東亜製粉、(旧)日清製粉、大日本製粉、増田製粉所、大里製粉所など大規模な製粉会社が相次いで設立された。
明治42(1909)年、鈴木商店は「官営札幌製粉場」の後身であり、かつて米田龍平が技師長兼支配人として腕を振るった「札幌製粉」を買収すると、小樽支店長の志水寅次郎が常務取締役(後・専務取締役)として役員に名を連ね、鈴木商店小樽支店は道内全域に札幌製粉の「赤星」「白星」ブランドの製品を拡販していった。
明治36(1903)年、「生産ということが人間の一番尊い仕事である」という強い信念を抱いていた金子直吉率いる鈴木商店は、門司市大里の大川の良質な水、豊富な石炭と安価な労賃、原料糖を産するジャワ島(インドネシア)に近い立地・利便性に着目し、日本初の臨海製糖工場となる大里製糖所(現・関門製糖)を設立する。
明治40(1907)年、鈴木商店は当時好成績をあげていた大里製糖所を、競合先であった先発大手の大日本製糖(現・大日本明治製糖)に売却することにより400万円という巨額の余剰資金を獲得する。そして、このことが鈴木商店の製造業を始めとする経営多角化による更なる飛躍のきっかけとなった。
鈴木商店はこの余剰資金を背景にして、その後も大里地区に再製塩工場[明治43年]、帝国麦酒(現・サッポロビール)[明治45年]、大里酒精製造所(現・ニッカウヰスキー)[大正3年]、大里精米所[大正4年]、神戸製鋼所門司工場(現・神鋼メタルプロダクツ)[大正6年]、日本冶金(現・東邦金属)[大正7年]など、明治後期から大正中期にかけて工場を次々に建設していったが、その内の一つが「大里製粉所」である。
明治43(1910)年、鈴木商店は門司市大里への製粉会社進出計画を発表すると、直ちに所有する大里関税仮置場の隣接地8,000坪に生粉能力1,600バーレルの大規模工場を建設し翌明治44(1911)年、「大里製粉所」を設立し、工場責任者に米田龍平を迎えて操業を開始した。
米田は前記の札幌製粉に勤務した後の明治39(1906)年、イギリス人経営の香港製粉に招かれ製粉技師(後・副支配人)として活躍したが、明治43(1910)年に同社が解散したため帰国すると、知遇を得た後藤新平の紹介により鈴木商店に入社し、大里製粉所に赴任した。大里製粉所は米田の指導の下で「赤ダイヤ」「緑ダイヤ」の商標で製品を売出し、たちまち北九州から中国地方にまで販路を伸ばした。
なお、大里製粉所は創業当初は香港から中古の製粉機を輸入して使用していたが、その後アメリカ・ノーダイク社製の最新鋭機を備えた近代的製粉工場へと変貌を遂げる。
新設の大製粉会社が次々に操業を開始した結果、国内の機械製粉の生粉能力は急速に向上し小麦粉はたちまち供給過剰となった。一方で、わが国は日露戦争終結後の反動不況に見舞われ、製粉業界は小麦粉相場の下落・製品の乱売という事態を招き、製粉各社は軒並み苦境に陥った。
この事態を受けて製粉業界では経営統合が進行し、(旧)日清製粉は館林製粉と合併して「新生・日清製粉」(現在の日清製粉)となり、日本製粉は明治製粉と帝国製粉を吸収合併した。