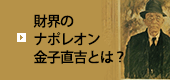日本セルロイド人造絹糸(現・ダイセル)設立の歴史④
大手セルロイド会社8社が合同し、大日本セルロイドを設立
大正7(1918)年11月に第一次世界大戦が終結すると、反動不況により一転してセルロイドは大幅な供給過剰となった。大戦前は日本セルロイド人造絹糸、堺セルロイド合わせて月産8~9万ポンド(約40トン)に過ぎなかったが、その後新規参入が相次ぎ、月産35~40万ポンド(約160~180トン)に拡大。また工場の乱立により、樟脳の原料であるクスノキの乱伐も危惧される状況にあった。
そこで堺セルロイド専務の森田茂吉が台湾総督府専売局長・賀來佐賀太郎に相談した結果、専売局は有力なセルロイド会社のすべてが1社に統合されるならば、これに対して原料樟脳を一手に供給するという方針が決定された。この専売局の決定により、同局の斡旋を受けて紆余曲折を経ながらも大正8(1919)年9月8日に創立総会が開催され、日本セルロイド人造絹糸(合同比率21%)、堺セルロイド(同48%)、大阪繊維工業(同16%)ほか合計8社が合併し、「大日本セルロイド」が誕生する。この大日本セルロイドの大株主は、三井、岩井、鈴木が占めた。
創立時の役員には、三井出身の森田茂吉が社長に、専務取締役には鈴木商店出身の嶋村足穂、常務取締役には岩井商店出身の西宗茂二が就任した。なお、同年、鈴木商店の元東京支店長・長崎英造(後・昭和石油社長)と松田茂太郎も取締役に就任している。
新会社設立後、大戦終結の反動不況が本格化する。大正9(1920)年には神崎工場、網干工場、東京工場の3工場が操業を停止し、かろうじて堺工場のみが運転を続け、人員整理、減資等を断行することとなった。結局、網干工場は大正9(1920)年~13(1924)年までの間操業を休止する。その間、網干町の財源は深刻な痛手を受け、同町は町会で委員を選出し堺本社に工場再開の嘆願を行っている。
大日本セルロイドは、同社の経営に影響を及ぼすセルロイド生地の販売代理店および加工業者の健全な発展をはかることを創立当初からの基本理念とし、その育成・援助には特に配慮し、同社と一体の関係となっていった。その後も、同社と販売代理店・加工業者との関係は、あたかも親と子のような関係に培われ、連綿と続いていった。
大正時代後半の慢性的な不況下にあって、セルロイド業界の回復は比較的早く、大正10(1921)年を底として漸次回復に向かい、さらに欧米諸国の好況と同社の積極的な販路開拓によって輸出も活発化し、大正11(1922)年5月期には配当を実施。その後も需要が増加し、唯一稼働していた堺工場だけでは応じきれなくなったため、大正11年12月に東京工場を、大正13(1924)年6月には網干工場を再開した。網干の町民は歓喜し、再び網干の町は活気を取り戻した。
昭和2(1927)年に発生した金融恐慌、昭和4(1929)年10月に始まった世界恐慌下では工場閉鎖や人員整理など厳しい対応を迫られたが、昭和7、8年頃から景気回復とともにセルロイド業界も好転。堺、網干の両工場は多忙を極めた。この頃、それまで地道に継続してきたセルロイドの品質向上の研究が大きく開花し、また長年にわたって海外市場の開拓につとめてきた努力が実を結び、輸出も飛躍的に伸長した。
昭和9(1934)年には網干工場に優良製品工場を建設することが決議され、当時の技術水準としては世界的に第一級と評価される最新鋭工場が完成する。ここにおいて、同社は品質面、生産量のいずれにおいてもまさに世界一となり、その製品は世界40数カ国に輸出されるまでに発展した。
この間、鈴木商店は昭和2(1927)年に破綻を余儀なくされ、鈴木商店のセルロイド事業への関与はここに終りを告げた。