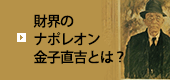破綻の原因
財務体質の脆弱さと戦線縮小の遅れが命取りに
明治末期、後藤新平を介して始まった台湾銀行との二人三脚で頂点に駆け上った鈴木商店は、パートナー・台銀の絶縁宣言によりあえなく昭和の荒海に沈んだ。
「生産こそ最も尊い行為」という金子直吉の経営哲学から自前の機関銀行を持たなかった。唯一の鈴木系銀行の六十五銀行も規模は小さく、辰巳屋藤田商店の藤田助七が頭取を務めていた大正11(1922)年末、同時期の台湾銀行と比べると預金高で1.7%、貸出高で0.4%に過ぎず、とても鈴木商店を支えることができる規模ではなかった。
他財閥のように金融機関を自前で持たず、専ら台湾銀行の融資に依存したこと、さらに株式公開による資金調達の道も自ら閉ざしてしまった財務体質の脆弱さが鈴木のアキレス腱であった。金子直吉には鈴木家のために尽くすという信念が強くあり、稼いだ利益を資金しか拠出しない他株主に分配するという近代的な考え方を受け入れることができなかった。
一方の台湾を基盤とする特殊銀行ながら、国内に有力な融資先を持たない台湾銀行が金子の旺盛な事業欲に応える形で鈴木と結びついたのは至極当然であった。
第一次世界大戦の戦時景気に乗って鈴木商店は戦線を拡げ、台湾銀行の鈴木商店への貸出しは急激に膨らむ。戦争終結の気配から敏感な嗅覚の金子は退却指示を発するも若手社員の反対にあい、事業縮小の時機を逸してしまった。金子の不安は的中し、景気は一転して落ち込む中、業績悪化により台銀からの借入れは拡大の悪循環に陥ってしまう。後年、金子は統制力を失ったことが取り返しのつかない事態になったと悔やんだ。