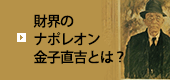豊年製油(現・J-オイルミルズ)設立の歴史①
南満州鉄道(満鉄)が「ベンジン抽出法」による大豆の搾油技術を研究・開発
明治時代に入ると、都市部では文明開化のかけ声とともに欧米の食文化がなだれを打つように流入し、食用油の利用が急速に進んだ。当時はまだナタネ、綿実、ゴマなどの植物油が中心であり、大豆が搾油原料として使用されることはほとんどなかった。しかし、日清戦争後は主に中国東北部から大豆油粕(脱脂大豆の当時の呼称。豆粕とも呼ばれていた)が有機肥料の原料として輸入されはじめ、大豆が搾油原料として注目されるようになる。
当時の中国東北部の製油技術は、畜力で石臼を回して大豆を砕き、楔で搾るという単純な方法で、1工場1日当たりの大豆処理量は25トン程度であった。ところが、日清戦争後、蒸気機関を使用しローラーによって大豆を砕く方法が導入され、また、蒸豆の圧搾に手押しの螺旋式機械を使用する方法も始まり、製油法は一気に機械化されていった。(これらは「圧搾法」と呼ばれる技術である)
こうして製油法が近代化されるとともに、中国における生産の中心地は大連、ハルビンへと移っていき、日本向け需要にも対応していくようになる。小寺壮吉は日露戦争後に遼寧省営口に水圧式油房(大豆搾油企業)を設立したが、これが中国北東部における日本人初の油房設立であった。
明治35(1902)年、福井県敦賀でわが国初の大豆搾油企業として、大和田製油所が「圧搾法」により大豆油の製造を開始する。当時は脱色、脱臭の研究も不十分で、大豆油そのものの評価は芳しくなかったが、一方で肥料としての大豆油粕の需要が旺盛であったため、明治30年代から40年代にかけて、大豆油粕を製造する企業が相次いで設立されていった。
日露戦争の結果、明治39(1906)年に国策会社として設立され各種特殊権益を獲得した南満州鉄道(満鉄)は、鉄道以外にも農産物などの産業開発を手掛け、特に満州の特産品である大豆、そして大豆搾油事業に注目した。そして、当時中国北東部において相次いで設立されていた油房が行っていた非効率な製油法を改善すべく翌明治40(1907)年10月、大連に「満鉄中央試験所」を開設する。
大正2(1913)年12月には大連埠頭の東、大連市外寺兒溝桟橋付近に試験工場を設けて、ドイツで開発された化学的抽出法である「ベンジン抽出法」(大豆を圧扁し、ベンジンを溶剤にして大豆油を抽出する技法)による特許権と機械類一式を購入し、大正3(1914)年3月より「満鉄豆油製造場(油房)」の名で試験的製造を開始した。
このベンジン抽出法は圧搾法に比べると設備投資は多額となったが、大豆油の収量は原料の大豆を100とすると約16%(圧搾法では10%)、豆粕中残留油分は約1%(圧搾法では約8%)、さらには豆粕タンパク質含有量は45%(圧搾法では40%)など圧倒的に優れた技術であった。満鉄豆油製造場は、大正4(1915)年春に所期の試験を終了。その結果、導入時の技術よりもさらに高能率の方法を開発することに成功する。
一方、大正初期におけるわが国の製油業はナタネ油が中心であり、大豆油は営利事業として成功したことはなかった。当時、鈴木商店は北海道、朝鮮から集荷した魚油を直営の魚油精製所にて精製して欧州等へ輸出していたことから、金子直吉は大豆油にも注目し、明治40(1907)年頃から安倍元松を主任として大豆搾油の研究をさせていた。
当時は満州産大豆油粕の肥料的価値が認められ、日本政府も農業生産力向上のため大豆油粕の普及を進めていた時期であり、金子が大豆に注目し、大豆搾油の商業化を考えるのも自然の流れであったと言えよう。
当時は、前述のように圧搾法では大豆油粕の残留油分が多く、蛋白含有量も少ないため肥料としては不向きであった。安倍はこの点を改善するために研究を進めたが、量産化の目途を付けることが出来ない状況にあった。このため、金子は大豆の一大産地である大連に人を派遣したところ、満鉄豆油製造場がベンジン抽出法により大豆搾油の商業化を試みていることが判明する。