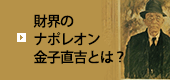大日本塩業(現・日塩)の歩み②
関東州において塩田開発に参入する
中国北東部の遼東半島は、かねて日本が天日製塩による安価な塩の産地として注目していた地域であった。しかし、日清戦争終結後にロシアがこの地域を租借してからは、貔子窩と普蘭店以外の塩田は著しく荒廃した。明治38(1905)年、この地が日露戦争後に「関東州」(*1)として日本の租借地になると、元々製塩の好適地であったことから、荒廃していたとは言え再開発の可能性が高いことに日本の企業家が着目し、塩田開発の機運が高まった。
(*1)「関東州」は遼東半島の西南部と付近に散在する長山列島、五島などの約40の島からなる区域(面積は3,367㎢で鳥取県よりやや小さく、大連港、旅順港の良港を擁する)で、統治のために「関東都督府」が置かれたことから日本国内では「関東州」と呼ばれ、大陸進出への橋頭堡として太平洋戦争終結に至るまでの40年間、日本は製塩業を始めとする各種産業の開発を進めていった。
関東州の空気は乾燥し、降水日数と降水量はともに少なく、風力は比較的強いため水分の蒸発は旺盛で、気候、海水、塩田の土質という天日製塩(*2)上の3つの条件を満たしており、台湾、朝鮮、内地(日本国内)の瀬戸内十州と比べても遜色のない製塩の好適地であった。
(*2)天日製塩法の塩田には種々の様式があるが、関東州においては揚水式と流下式の2種類に区別される。揚水式は、溜潮池または水溝内に溜めた海水を水車や風車などの揚水機によって蒸発池に注入する方式である。流下式は、溜潮池に溜めた海水を地盤の高低により自然に蒸発池に流下させる方式である。関東州の塩田はほとんどが流下式で、可能な限り人力を省き自然の力によった。なお、製塩時期は3月上旬から11月下旬までのおよそ8カ月で、梅雨期の7月中旬から8月中旬にかけては製塩を休止した。
関東州塩は天日製塩のため結晶粒が粗く(こぶし大のものも混じっていた)、また貯蔵方法が野積のため塵埃が付着するなどして色相も劣ることは否めなかった。しかし成分については純塩分の含有量が多く、内地の2等塩(NaCl85%以上が2等塩、80%以上が3等塩)に匹敵し、さらに製塩上の各種改善を加えれば東洋では困難視されていたNaCl 95%以上の精良塩を得ることも不可能ではないと見られていた。
関東都督府は塩田開発者を募ることとなり、塩の専売制は適用せず許可制として土地は無償で貸し付けるが、大規模経営が可能な経営者を選定する方針とした。このため、関東州における塩田開発の出願者は55件にも達したが小規模経営の出願者は許可されず、明治39(1906)年に許可されたのは日本食塩コークスほか3社(満漢塩業、満漢起業、宅合名会社)と2個人にすぎなかった。
関東州において塩田開発の許可を得た日本人経営者は天日製塩の経験者は皆無であり、築田の技術も製塩に関する資料も持ち合わせていなかった。そんな中で、日本食塩コークスは双島湾、東老灘、普蘭店・河棗兒房間の合計4,000町歩の塩田開設許可を得た。
なお、当時の関東州の塩田は次の5管内、14塩場に区別されていた。
貔子窩管内(碧流河、東老灘、夾心子、賛子河の各塩場)、普蘭店管内(普蘭店、五島の各塩場)、旅順管内(旅順、羊頭湾、双島湾、営城子の各塩場)、大連管内(老虎灘、沙河口の各塩場)、金州管内(薫家溝、干鳥子の各塩場)
明治39(1906)年8月、同社は取締役の中村邦治郎を関東州に派遣して塩田開設工事を督励し、あわせて社員を増派、さらに、台湾の天日製塩を経験した後に同社に技師長として入社した萱場三郎を始めとする優秀な技術者を擁して研究を重ね、数々の困難を乗り越えて工事を進めていった。
関東州で日本人による塩田開発が始まった当時は、日本国内では塩専売制(*3)が実施され、台湾塩が移入されていた。しかも国内塩は平年では生産過剰気味であったことから、日本政府、とりわけ大蔵省専売局は関東州の塩田開発には及び腰であったといわれる。
(*3)前記のとおり、日本国内では明治38(1905)年6月1日に塩専売制度が実施された。
このような状況下ではあったが、前記のとおり同社が日露戦争による軍需景気に乗じて固型食塩、粉末味噌、コークスの販売で巨利を得た直後であったことに加えて、関西の有力実業家の資金的なバックアップもあって同社の塩田開発は順調に進展した。
塩田の経営は大別すると自作と小作があり、関東州では中国人による小規模塩田経営は自作方式で、日本人による大規模塩田経営は主に塩田主にとって比較的軽微なリスクで安全に収益をあげることができる小作方式で行われた。小作方式は小作人(すべて中国人の採塩経験者で、地方の有力者であった)が塩田主と小作契約を結び、生産される塩はすべて契約価格(賠償価格)で塩田主に引き渡される方式で、日本食塩コークスもこの方式によった。
明治39(1906)年6月、同社は年間6,000トン以内という条件付きながら関東州塩の「輸入取扱人」に指定され、あわせて輸移入塩の国内販売の「特別元売捌人」にも指定され、内地の大蔵省専売局、工業家、漁業家、さらに朝鮮方面(*4)へと販路を広げ、事業を拡大していった。明治39(1906)年12月、日本食塩コークスは讃岐コークス製塩を合併し、分工場とした。
(*4)明治43(1910)年8月、日本は朝鮮(韓国)を併合し、京城(現在のソウル)に朝鮮総督府を置いたが、当時の朝鮮は他の外地と異なり当地の産塩では需要を満たせなかったため、関東州塩が供給された。
明治41(1908)年2月、日本食塩コークスは社名を「大日本塩業株式会社」に変更すると、明治45(1912)年から大正4(1915)年にかけて関東州の東洋製塩、満漢塩業、東亜塩業(鈴木商店系列)などが資金、技術、販路等の面から経営が苦しくなると、それらの製塩会社を次々に吸収合併(*5)していった。
(*5)明治45(1912)年7月、東洋製塩を合併。大正4(1915)年1月、満漢塩業を合併。大正4(1915)年8月、東亜塩業(鈴木商店系列)を合併。大正5(1916)年、村井文太の事業を合併。
これにより、同社の塩田開設面積は2,600町歩となり、大正5(1916)年には関東州における日本人の塩田は大日本塩業の一手に帰し、日本の塩田経営者として独占的な地位を獲得した。