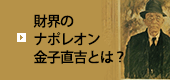鳥羽造船所電機工場(現・シンフォニアテクノロジー)の歴史⑧
神戸製鋼所の電機部門が独立し神鋼電機が発足するも、苦境が続く
終戦後の数年はGHQ(連合国総司令部)の非軍事化という旧軍需企業への厳しい姿勢により、神戸製鋼所の経営陣にとって試練の時期となった。
昭和21(1946)年10月、戦時補償特別処理法が公布されたことにより戦時補償が打ち切られたため、神戸製鋼所は救済策として新たに設けられた特別経理会社に指定され、昭和21年10月11日以前の旧勘定とそれ以降の新勘定の2勘定で決算処理を行うこととなった。
人事面では昭和20(1945)年9月17日、田宮嘉右衛門は重役会で皆が社長への留任を懇請したが、「重役を減員し多数社員を解雇するについては率先垂範する必要がある。定款を変更して会長となるようお手盛りはいけない。断じて責任を逃れようとはしない」と社長辞任を言明し、相談役に就任した。
同年11月、神戸製鋼所は社長 浅田長平、副社長 田子富彦、常務取締役 小田嶋修三、高橋良次、取締役 高畑誠一、町永三郎、監査役 竹岡筍三 という役員構成となったが昭和21(1946)年12月、役員の大部分は辞任し、新社長に町永三郎、常務取締役に高橋良次、杉本正幸、取締役に松井悦蔵がそれぞれ就任した。
昭和22(1947)年にはGHQの占領政策の一環として、戦争・軍需に協力した財界人への公職追放令が下り、神戸製鋼所においては田宮、浅田、小田嶋ら役員4名が財界追放の処分を受けた。
さらに、GHQは神戸製鋼所に対して、徹底的に企業分割を実施し旧会社と支配関係のない数社の小資本規模の会社にすることを求めてきた。神戸製鋼所はその指示に従い、最終的には本体の神戸製鋼所を残すことは断念して解散し、新たに6つの第二会社を設立するという案(6分割案)をGHQに提出した。
しかし、当時米国内ではソビエト連邦への対抗上、日本を復興させるべきという意見が強まっていたため神戸製鋼所は急ぎ重役会を開催し、制定準備が進んでいた「過度経済力集中排除法」が緩和されるという説を考慮し、従来の6分割案を排して3分割案(神戸製鋼所、神鋼金属工業、神鋼電機)とすることを決定した。
結局、集中排除法の運用は緩和され昭和23(1948)年11月、神戸製鋼所において計画されていた3分割案はその必要性と拘束力を失った。しかし、神戸製鋼所ではこれをよしとせず、同法の本来の精神を汲み取り、さらに企業合理化をはかる意味合いからも、当初の計画通り自主的に会社を製鋼、金属、電機の3部門に分割することとし同年11月、神戸製鋼所を残し、新たに金属および電機の2つの第2会社を設立する方針を最終決定した。
昭和24(1949)年6月、神戸製鋼所の再建整備計画は当局に許可され、電機部門については計画通り「神鋼電機株式会社」として設立されることとなった。
戦後逸早く生産復興に立ち上がり、繁忙状態を呈していた電機本部所属の4工場(鳥羽、山田、松阪、東京)であったが、昭和24(1949)年に入ると様相は一変した。同年2月にGHQ財政金融顧問として来日したドッジ公使の勧告に従って強行されたいわゆる「ドッジライン」により激しいインフレは収束したものの、急転してデフレの様相を呈し、急激な購買力の減退による需要の衰退の波が4工場を直撃した。
昭和24(1949)年6月、電機本部は新会社の将来を考慮し、徹底的な体質強化策を講じることとし、鳥羽、山田、東京の3工場の人員整理(679人)と採算不良の製品が多い松阪工場の閉鎖を主内容とする合理化対策を発表した。
会社は連日工場閉鎖そのものに反対する労組との激しい団体交渉の末に同年8月、ようやく妥結を迎えた。これに伴い、戦時下の昭和18(1943)年に開設された55万㎡という広大な敷地を有していた松阪工場は、わずか6年足らずでその歴史の幕を閉じた。
昭和24(1949)年8月18日、「神鋼電機株式会社」(現・シンフォニアテクノロジー)が正式に発足した。発足に際し神戸製鋼所から引き継いだ固定資産および棚卸資産(現物出資)は4,549万円、現金が5,451万円の計1億円で、これが資本金となった。発足時の役員は、取締役社長 杉本正幸(*)、常務取締役 間島一栄、山崎幸一郎、取締役 三好忠一、佐藤昌吉、小林保一、常勤監査役 安藤杢、監査役 益田元亮 であった。
(*)初代社長の杉本は、新会社発足前は日本勧業銀行(現・みずほ銀行)監査役を経て神戸製鋼所の経理担当重役として迎えられ、神戸製鋼所の分割に際しては東京本社のトップとしてその任に当たった。
新会社の本社事務所は東京都中央区西八丁堀にある梅ビルに置かれたが、同社にはビルの購入・改装資金の調達能力が乏しかったため、やむなく神戸製鋼所に購入してもらい借用した。生産拠点は鳥羽工場、山田工場、東京工場の3工場、従業員数は2,650人であった。
戦後のわが国の経済情勢は一向に好転する気配がなく、倒産・整理が続出した。神戸製鋼所の電気部門はもともと他の部門に比べて基盤が強固でなかったことに加え、営業体制も弱体だったこと、当時は売り上げの拡大に寄与するだけの製品にも恵まれていなかったこと等の理由により、神鋼電機は打ち続く不況に耐えられず、業績不振が甚だしく一気に資金難に陥った。
同社は日常業務にかかわる経営資金にも事欠く有様で、在庫の資材を切り売りしながら、辛うじてその場をしのぐといった綱渡り的資金繰りも再三であった。これに伴い、銀行からの借入金は増加する一方で、従業員の給料も遅配が常態化し、前途は暗澹たるものであった。
銀行出身で財務会計に精通した杉本社長は、同社のこうした危機的状況を乗り越えるべく社債の発行を目論んだ。この社債が発行できないとなると会社の破綻が目に見えていたため経営陣は全員必死で、ついには「役員一同、生命をかけて実現を期する」という誓約書まで日銀当局に提出するほどであった。
昭和25(1950)年1月末、幹事会社の第一銀行や幹事証券会社の山一證券の側面からの援助もあって、同社はようやく当局の認可を受け、第1回社債1億円の発行に漕ぎ着けた。社債の購入元は当時資金的に余裕があった地方銀行や相互銀行、農協であったが、経営陣は手分けして、全国のほとんどの金融機関を駆け回り、社債の購入を頼み込んだという。当時これだけの資金が調達できたことは、逼迫状態にあった同社にとって文字通り干天に慈雨であり、ようやく急場をしのぐことができた。
同年3月20日、同社は第1期決算(昭和24年8月18日~昭和25年3月20日)を迎えた。業績は売上高3億5,900万円に対し、業績不振を極めたわりには100万円ほどの小幅な赤字で終わった。なお、この年、GHQによる公職追放で退職していた小田嶋修三は追放が解かれると同時に同社に招へいされ、顧問役として復帰して経営面・技術面で経営陣をサポートしていくことになった。