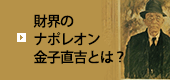金子直吉の幼少期、鈴木商店入店
土佐の辺境の地から開国の息吹の漂う港神戸へ
慶応2(1866)年、伊予との国境に近い土佐・吾川郡名野川村(現在の高知県吾川郡仁淀川町名野川)に生まれた金子直吉は、父甚七が営む呉服反物の商売が振るわなくなり、直吉が5、6歳の頃、一家とともに名野川村を引き上げ高知市内に移り住んだ。
高知・乗出(のりだし)での生活は、極貧を極め、家計を助けるため幼くして丁稚奉公に出るようになった。奉公先を転々と変わるうち、農人町の質店・傍士久万次(ほうじくまじ)の下に落ち着く。傍士質店には6年ほど勤め、やがて番頭に取り立てられた。この間、質草となった多種多様な書物を読み漁り、また主人が裁判沙汰に巻き込まれると主人のために訴訟に立ち、相手方の著名な弁護士を相手に勝訴するなど直吉の商売の骨格は、まさにこの「質屋大学」の時期に造られたといわれる。
傍士久万次は、やがて質店を廃業して砂糖商に転業、ここに直吉と鈴木商店との接点が生まれた。傍士の紹介で明治19(1886)年、直吉20歳の時、神戸の鈴木商店に雇われた。この時直吉と鈴木商店の仲立ちをしたのは、この地を担当していた鈴木商店の柳田富士松であった。
気性の激しい主人・岩治郎の厳しいしつけに耐えかねて直吉は、土佐に逃げ帰ってしまうが、よねは呼び戻しの手を差し伸べ、柳田富士松を従え土佐まで迎えに行った。
明治27(1894)年、直吉28歳の時、主人・岩治郎が病に倒れ急逝する。未亡人となったよねを中心とし、柳田富士松、直吉の両番頭による新生鈴木商店がスタートした。
再出発早々、金子直吉は担当する樟脳の相場を見誤り、ハタ売り(カラ売り)で莫大な損害を出してしまう。金子はハラ切り覚悟で居留地の外国商館と折衝し、一方の「お家さん」こと鈴木よねは、金子を咎めず、親族を頼りこの存亡の危機を乗り切る。