辰巳会・会報「たつみ」シリーズ(70)「たつみ第70号」をご紹介します。
2025.2.8.
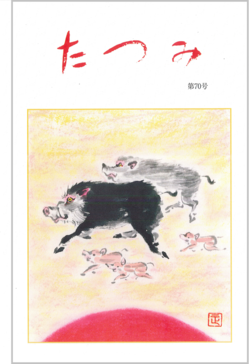 「たつみ第70号」は、平成19(2007)年1月23日に発行されました。本号では、"金子直吉"の人間像を知る特集として、金子と交遊があり金子をよく知る人物が著した書籍から金子に関する記述を抜粋して紹介しています。(一部「たつみ第57号」に掲載済みの記事があります。)
「たつみ第70号」は、平成19(2007)年1月23日に発行されました。本号では、"金子直吉"の人間像を知る特集として、金子と交遊があり金子をよく知る人物が著した書籍から金子に関する記述を抜粋して紹介しています。(一部「たつみ第57号」に掲載済みの記事があります。)
◇金子直吉について書かれた書籍紹介
1.「小笠原三九郎伝」常盤嘉治著 ~第五章「台銀復帰」より抜粋~(たつみ第70号)
(財)関東学院理事や日本協同党党員でもあった常盤嘉治が昭和32(1957)年に著した「現代日本人物伝叢書(第一)小笠原三九郎伝」の一部を抜粋。
戦後、幣原内閣で商工大臣(昭和20(1945)年)、第4次吉田内閣で農林大臣、通商産業大臣(昭和27(1952)年)、第5次吉田内閣で大蔵大臣(昭和28(1953)年)を歴任した小笠原三九郎は、政界入りする以前は実業家として活躍した。
東京帝国大学卒業後、直ちに台湾銀行に入行、その後華僑と日本との合同銀行「華南銀行」専務に転じたが、やがて台湾銀行に復帰、審査第一部長として台湾銀行不良債権処理に携わる。
取り分け台湾銀行の融資が膨れ上がる鈴木商店に対し鈴木とその関係会社の整理に着手。金子の巧みな金借り戦法を封じることが肝要と結論付けた。鈴木商店への貸付金の整理が進まないのは、金子の主家に対する忠義心に幻惑されて貸増しを繰り返してきたことが一大原因とした。
小笠原は、私利私欲は一切無いという金子の釈明に対し、所有欲は無いかも知れないが使用欲については天下無類だ。今後、私欲は無いという言い訳は通用しないと金子を牽制した。(詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。)
2.「人使い金使い名人伝」中村竹二編 ~抜粋「商機の生神様 金子直吉」~(たつみ第70号)
「処世のコツ」や「もうける法、もうけた人」等の著書で知られる中村竹二が昭和28(1953)年、実業之日本社から著した「人使い金使い名人伝」のうち、"商機の生神様 金子直吉"の中で長崎英造(元合同油脂社長)と住田正一(元国際汽船取締役、東京都副知事)のいずれも金子直吉の最側近として係わった二人による金子の人となりを綴った記述の抜粋。(この記述は、「たつみ57号」に既に掲載しており、再掲載)
数ある金子のエピソードの中で印象的なのは、「世の中に、本と人間ほど安いものはない」という金子の口癖があった。本も人間も本当にその価値を知って活用すれば得られるものは、どれほど大きいかも知れない。
毎期、業績により賞与金を出す際、失敗者へは、お家さんや柳田さんに相談して"見舞金"を出していた。金子の心遣いを知り、一度でも賞与金代わりの見舞金を受けた者は、終生の努力を誓わずにはいられなかったと。(詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。)
3.「徳の人・智の人・勇の人」藤原銀次郎著 ~「金子直吉と山本条太郎」より抜粋~ 昭和31(1956)年出版(たつみ第70号)
明治中期、三井銀行を経て三井の経営する富岡製糸場支配人、三井物産上海支店長、王子製紙専務・社長を歴任した後、政界に転じ、商工大臣(米内内閣)、国務大臣(東条内閣)、軍需大臣(小磯内閣)を務めた筆者が、その著書のなかで自身が尊敬し、畏敬する実業界の大先輩と認める金子直吉と山本条太郎について私見を披歴している。(この記事も「たつみ第57号」に既に掲載されており、再掲載である。)
金子については、実業界に於ける大成功者であると同時に大失敗者でもあるという両面を有している。"前期金子"と"後期金子"として、金子の成功の偉大さと破綻失脚の遺憾を痛感させられた。
我が産業経済界の一大先覚者として見直さなければならない。また、何が金子を失脚に追い込んだかを再検討すべきと結んでいる。(詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。)
藤原銀次郎は、本著に先立つ昭和27(1952)年、「天才的事業家金子直吉を見直す」を著し、金子の功績を高く評価している。
4.「財界太平記」三宅晴輝著 ~第三編「日本財界に黄金時代来る」より抜粋~(たつみ第70号)
ビジネス書や経済誌を発行する東洋経済新報社の記者として活躍また昭和期の経済評論家として知られる著者が、昭和27(1952)年に出版した「財界太平記」の中で、"日本財界に黄金時代来る"と題し、「戦争成金の花形 鈴木商店」を掲載した。
先の欧州大戦(第一次世界大戦)では、その混乱期に多くの戦争成金が誕生し、やがて反動不況になると殆どが消え去ったが、この時代に最も華やかに躍動した鈴木商店は正に戦争成金の花形であり、わが国財界の黄金期を代表する企業でもあった。(詳細は、関連リンクをご覧ください。)なお、本文中に鈴木商店の設立を明治35年としているのは、合名会社への改組時期で、鈴木商店の創業時からの歴史を振り返っていることから明治7年の創業と読み替えて欲しい。また、有名な"天下三分の宣誓書"の手紙が「金子直吉伝」に収録されているとの記述は、「金子直吉遺芳集」の誤り。
5.「北村徳太郎随想集」より抜粋 ~はなしの漫歩抄 ー岩下清周と金子直吉~(たつみ第70号)
播磨造船所拡張期に事務課長として辣腕を振るい、鈴木商店の破綻後は、金子直吉の側近として破綻処理を担った北村徳太郎が昭和34(1959)年に著した著書の中で、共に金子の薫陶を受けた大屋晋三(帝人会長、当時)との対談を抜粋して紹介。
北村が尊敬する人物として、鈴木商店に入社する以前に勤めた北浜銀行時代に秘書として仕えた岩下清周と金子直吉には、多くの共通点があったと。
北村、大屋の共感する金子直吉の人となりは、洞察力の鋭さ、人の個性を見極めて卓越した人の使い方と云う。人の短所ではなく、長所だけを掴み人を活かすことから、鈴木の全盛時には何千人の社員が皆"金子さん、金子さん"と尊敬を集めていた。(詳細は、下記の関連リンクをご覧ください。)
◇「経済野話」序 金子直吉(たつみ第70号)
金子直吉名で刊行された唯一の本著は、大正13(1924)年6月に初版が出され、昭和8(1933)年までに6版が出版された。本号ではその「序」のみ紹介され、次号以降で第1章から第9章までが掲載される。
大正9(1920)年以降、わが国の財界の大動揺の原因は如何なるものか等々、日頃から日本の経済界の実情等について考えていることを語った内容を側近の住田正一が口述筆記して著書に纏めたもの。この口述は、金子が頻繁に上京の折、定宿として長期で借り切っている東京ステーションホテル20号室で繰り返し行われたと云う。(詳細は、関連リンクをご覧ください。)
◇「辰巳会ゆかりの祥龍寺の歴史(その二)」菅應峰(たつみ第70号)
「たつみ第68号」に続き祥龍寺第三世住職管応峰(謙堂応峰)による同寺の歴史(その二)を紹介する。
大化年間649年頃、開基法道仙人によって開かれた"広国山祥龍寺"は、平清盛による福原遷都の頃には大いに栄えたが、その後荒廃が進んだ。応仁年間には復興、本山妙心寺派が黄檗山萬福寺の傘下となると禅宗の寺院として歩むも江戸宝暦年間の火災により灰燼に帰し、寛政初め(1790年頃)には廃寺となっていた。(詳細は、関連リンクをご覧ください。)
*昭和2(1927)年、鈴木よね他の寄進により再興なった"宝珠山(山号を変更)祥龍寺"の中興開祖(一世住職)となった碧層軒五葉愚渓老師は、妙心寺派第551世管長でもあった。現住職は第五世光岡靖玄氏(悠山靖玄)が勤めている。
◇「祖父 柳田富士松を探る」柳田辰巳(たつみ第70号)
金子直吉との名コンビで鈴木商店の発展を支えた柳田富士松の孫の筆者が祖父の足跡を振り返る。昭和3(1928)年1月24日生れの筆者は、祖父と共に生きた時間は、僅か2週間のため祖父の面影も記憶も全く無く、父母を始め親族より側聞したことしか記憶にない。その中で興味深いのは、大里製糖所の売却代金の使途について、祖父・富士松は阪神間に土地を買おうと云ったのに対し、金子翁は、工業に投資しようと主張。祖父と金子さんの意見が合わなかった唯一の出来事だったと聞いていた。
祖父の思い出について、祥龍寺に残る祖父の頌徳碑や、後に発行された白石友治著「柳田富士松伝」を基に振り返っている。(詳細は、関連リンクをご覧ください。)

