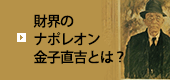神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の第28回「盟友2人 海運に参入」をご紹介します。
2017.1.11.
神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の本編「第4部 荒波、そして(28) 盟友2人 海運に参入 大戦終結 反動不況が襲う」が、1月8日(日)の神戸新聞に掲載されました。
今回の記事は、大正7(1918)年11月27日に川崎造船所社長の松方幸次郎がロンドンから2年8カ月ぶりに帰国するところから始まります。続いて、松方が第一次世界大戦終結に伴う過剰船腹(大量のストックボート在庫)を活用すべく川崎汽船を設立したこと、さらに松方がトップを兼ねる川崎造船所、川崎汽船、国際汽船の3社が共同で鈴木商店を総代理店として船舶を運行する「Kライン」が誕生するも現実は厳しかったこと、鈴木商店はKライン運行の差配をしたロンドン支店長の高畑誠一の尽力によりクロード法による空中窒素固定法の特許権を買い取るが、この頃から鈴木商店の台所事情が悪化し、購入額の半分を高畑が自ら蓄えておいた資金から支払ったことなどが描かれています。
 鈴木商店本店焼き打ち事件のショックから3カ月後の大正7(1918)年11月、第一次世界大戦の終結という事実が伝えられます。(左の写真は東京・日比谷公園における大戦終結祝賀会の様子です)
鈴木商店本店焼き打ち事件のショックから3カ月後の大正7(1918)年11月、第一次世界大戦の終結という事実が伝えられます。(左の写真は東京・日比谷公園における大戦終結祝賀会の様子です)
わが国は大戦勃発により需要が増大、物価高騰により生産活動が活発化し、鈴木商店は貿易そしてモノづくりにおいて日本の産業を牽引していました。
しかし、大戦の終結により日本経済はしばらくの間は戦後の復興需要に支えられ好調に推移しましたが、交戦国の復興とも相まって大正9(1920)年春ごろから日本の大正バブルは終結に向かい、たちまちにして急激な反動不況に突入しました。
それまでのインフレから一転猛烈なデフレがわが国を襲い、船舶をはじめ様々な物資の市況が急落し大正9(1920)年3月15日には東京株式市場が大暴落し、2日間立会が停止されました。
船価は翌年1月には半値を割り込んでなお下落を続けました。船価(トン当たり)は大正4(1915)年時を100円として、大正7(1918)年には900円まで急騰、大正10(1921)年には100円まで急落します。
 金子直吉はこの一大ショックに対して直ちに対応をはかります。大正7(1918)年に播磨造船所と鳥羽造船所を浪華造船所とともに鈴木傘下の帝国汽船と合併させます。これにより両造船所はそれぞれ帝国汽船播磨造船工場、帝国汽船鳥羽造船工場となりました。
金子直吉はこの一大ショックに対して直ちに対応をはかります。大正7(1918)年に播磨造船所と鳥羽造船所を浪華造船所とともに鈴木傘下の帝国汽船と合併させます。これにより両造船所はそれぞれ帝国汽船播磨造船工場、帝国汽船鳥羽造船工場となりました。
※その後大戦後の不況は予想以上に深刻となり、大正10(1921)年、鈴木商店は帝国汽船の造船部門を神戸製鋼所に合併させます。結局、帝国汽船播磨造船所工場と帝国汽船鳥羽造船所工場は神戸製鋼所・造船部に移管される形となり、それぞれ神戸製鋼所の分工場、神戸製鋼所造船部播磨造船工場と同鳥羽造船工場となります。
金子直吉らの尽力により大正7(1918)年に成立した日米船鉄交換契約により造船業界は息を吹き返しましたが、大戦終結にともなう海運市況の低迷を受け、皮肉にも建造した船舶の多くは過剰となってしまいます。このような状況下、造船各社はストックボート(見込み生産による規格船)などの過剰船腹の運用先として新たな海運会社の設立を模索していました。
 金子直吉の盟友・松方幸次郎(左の写真)が社長を務める川崎造船所(現・川崎重工業)も例外ではなく、大量に建造した「ストックボート」の運用に腐心していた松方はロンドンから帰国し大正8(1919)年4月、川崎造船所の船舶部の所有船を継承して川崎汽船を設立します。
金子直吉の盟友・松方幸次郎(左の写真)が社長を務める川崎造船所(現・川崎重工業)も例外ではなく、大量に建造した「ストックボート」の運用に腐心していた松方はロンドンから帰国し大正8(1919)年4月、川崎造船所の船舶部の所有船を継承して川崎汽船を設立します。
同年7月、金子直吉の提案によって川崎造船所(松方幸次郎)・川崎汽船(川崎芳太郎)、鈴木商店(金子直吉)、浅野造船所(浅野総一郎)、浦賀船渠(山下亀三郎)、横浜鉄工所(内田信也)、日本汽船(中山説太郎)、橋本汽船(橋本喜造)、石川島造船所(渡邊嘉一)の9社、8船主が所有船舶を船価換算して船舶を現物出資し、さらに一部政府の融資援助を得て国策会社・国際汽船(現・商船三井)が設立されました。
 最大の出資者の川崎グループと鈴木商店分を合わせた出資比率は全体の70%超となり、川崎汽船内に事務所が設けられ、川崎汽船の川崎芳太郎(川崎造船所の創始者・川崎正蔵の養嗣子)が初代社長に(後に松方幸次郎が社長に就任します)、鈴木商店からは金子直吉が会長に、ロンドン支店長・高畑誠一が取締役に就任して共同海運会社がスタートしました。
最大の出資者の川崎グループと鈴木商店分を合わせた出資比率は全体の70%超となり、川崎汽船内に事務所が設けられ、川崎汽船の川崎芳太郎(川崎造船所の創始者・川崎正蔵の養嗣子)が初代社長に(後に松方幸次郎が社長に就任します)、鈴木商店からは金子直吉が会長に、ロンドン支店長・高畑誠一が取締役に就任して共同海運会社がスタートしました。
国際汽船設立にあたり鈴木商店が提供した船舶は、傘下の帝国汽船が播磨造船所で建造した百合丸(6,787㌧)、八重丸(6,871㌧)・テキサス丸(6,786㌧)(右の写真)など5隻の貨物船でした。
多くの社外船主からの提供を受けた国際汽船は、創立から1年が経った大正9(1920)年には60隻・32万4000総トンもの船隊をそろえ、日本郵船、大阪商船(現・商船三井)に続くわが国第3位の船主に浮上します。しかし、大戦後の不況は予想以上に深刻で用船料は下落の一途をたどり、国際汽船の経営に致命的な打撃をもたらしました。
当時川崎造船所・川崎汽船・国際汽船の3社の社長を兼任していた松方幸次郎はこの苦境を脱すべく大正10(1921)年、ロンドンにおいて鈴木商店を総代理店とし、川崎汽船、川崎造船所船舶部、国際汽船の3社が保有する船舶を一つの旗の下に共同運航する構想を表明し、大西洋を舞台とする「Kライン」(3社のイニシャルから命名)を発足させます。
なお、Kラインのファンネル(煙突部分)マークは、「赤地に白文字のK」というデザインが採用されました。
松方幸次郎については次の人物特集をご覧下さい。
人物特集>松方幸次郎
Kラインは鈴木商店ロンドン支店長・高畑誠一の差配により、大西洋を中心に欧州・アメリカ・アジアを結ぶ日本を介さない、いわゆる「三国間航路」(外国と外国を結ぶ航路)の開拓に注力しました。これは、Kラインが当時世界の主要船主のランキングで13位に入り、この大船隊が日本近海で運行されると船賃のさらなる低落が必至だったからです。
大正11(1922)年に入ると世界の景気は悪化の一途を辿り、船腹過剰状態は解消せず海運市況はなかなか好転しませんでした。このため、Kラインの経営は「鼠」(城山三郎著)に次のように記されているように苦しいものとなりました。
「日本のドックを出た船は、1年から2年にわたって1度も故国へ帰らず、日章旗をなびかせて、大西洋を往き戻りする。(中略) 外見ははなやかではあったが、市場から追い立てられた果ての商売。営利企業というには程遠く、ただ故国へ帰れぬために、彷徨を続けているのでもあった。それは鈴木商店をシンボライズする姿でもあった。」
国際汽船の経営はKラインの効果も反映されず、危機に瀕します。その結果昭和18(1943)年、国際汽船は政府の指導により大阪商船(現・商船三井)へと吸収合併されます。
 一方で、Kラインのスピリットは川崎汽船に脈々と受け継がれていきました。川崎汽船はその後幾多の経営環境の激変を乗り越えつつ業容を拡大し、現在では世界でも有数のコンテナサービスを展開、また日本で初めて自動車や液化天然ガス(LNG)の専用運搬船を導入するなど、日本郵船・商船三井に次いで国内第3位の地位を確立しています。
一方で、Kラインのスピリットは川崎汽船に脈々と受け継がれていきました。川崎汽船はその後幾多の経営環境の激変を乗り越えつつ業容を拡大し、現在では世界でも有数のコンテナサービスを展開、また日本で初めて自動車や液化天然ガス(LNG)の専用運搬船を導入するなど、日本郵船・商船三井に次いで国内第3位の地位を確立しています。
川崎汽船の通称は現在も「"K"Line」で、ファンネルマークも「赤地に白文字のK」と当時のまま変わっていません。(左の写真)
 Kラインの大船隊の運行を差配した鈴木商店ロンドン支店長・高畑誠一(左の写真)は当時わが国の企業家の誰もがそうであったように、空気中に無尽蔵に存在する窒素の人工的な固定化によりアンモニア・合成硫安(化学肥料)を製造する空中窒素固定法によるアンモニアの直接合成の企業化に強い関心を持っていました。
Kラインの大船隊の運行を差配した鈴木商店ロンドン支店長・高畑誠一(左の写真)は当時わが国の企業家の誰もがそうであったように、空気中に無尽蔵に存在する窒素の人工的な固定化によりアンモニア・合成硫安(化学肥料)を製造する空中窒素固定法によるアンモニアの直接合成の企業化に強い関心を持っていました。
そして常にアンテナを高くして情報収集に努めていた高畑は、フランスの大手化学メーカーのレール・リキッド社がクロード法による空中窒素固定法の特許権を保有していることを突き止め大正11(1922)年初、鈴木商店は同社からこの特許権を購入します。
鈴木商店がレール・リキッド社に支払う特許料は50万ポンドに決定しましたが、金子直吉から高畑へは半分の25万ポンドしか送金されませんでした。残りの半分はどうしても都合がつかないため、結局高畑はこの不足分を自ら砂糖の取引で儲けて貯めておいた資金から支払いました。
実は鈴木商店の資金繰りはこの頃からかなり苦しくなっていたのです。売上高で三井物産を凌駕するまでに成長した鈴木商店でしたが、この大戦後の反動恐慌ともいうべき不況により受けた打撃は「神戸の鈴木」から「世界の鈴木」へと成長が急であっただけに甚大で、これを機に鈴木商店の業績は悪化の一途を辿り始めました。
下記関連リンクの神戸新聞社・電子版「神戸新聞NEXT」から記事の一部をご覧下いただくことができます。