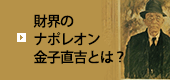神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の第30回「宿命のパートナー」をご紹介します。
2017.1.22.
神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の本編「第4部 荒波、そして(30) 宿命のパートナー 拡大路線 銀行と二人三脚」が、1月22日(日)の神戸新聞に掲載されました。
今回の記事は、鈴木商店と台湾銀行が抜き差しならない宿命のパートナーとなった経緯から始まります。続いて、第一次世界大戦終結に伴う反動不況により神戸の川崎造船所などで大きな労働争議が発生したこと、金子直吉が起死回生を狙っていた日本海軍の「八八艦隊」計画がワシントン軍縮会議により中止に追い込まれ鈴木商店がさらなる苦境に陥ったこと、台湾銀行が鈴木商店に対して介入に動いたこと、その後鈴木商店の信用失墜につながった「日粉問題」が起こったことなどが描かれています。
大正7(1918)年11月、鈴木商店本店焼き打ち事件から3か月後に第一次世界大戦が終結すると、日本経済はしばらくの間は戦後の復興需要に支えられ好調に推移しましたが、交戦国の復興とも相まって大正9(1920)年春ごろから急激な反動不況、すなわち、それまでのインフレから一転猛烈なデフレがわが国を襲い、船舶をはじめ様々な物資の市況が急落しました。
大正9(1920)年3月15日、東京株式市場が大暴落し2日間立会が停止されます。大正10(1921)年5月には七十四銀行の休業発表に端を発し、多くの銀行が取付け騒ぎに直面しました。
こうして大戦景気の反動は当時の識者の想像をはるかに超える大規模な形で日本経済に襲いかかり、加えてアメリカにおける反動恐慌の影響もあって、わが国は慢性的な大不況へと移行していきました。
 金子直吉の多大な尽力により成立した日米船鉄交換の成果ともいうべき国内残留船腹も、そのまま過剰船腹に転化してしまいました。
金子直吉の多大な尽力により成立した日米船鉄交換の成果ともいうべき国内残留船腹も、そのまま過剰船腹に転化してしまいました。
この頃、大戦終結の気配を嗅ぎ取っていた敏感な嗅覚の金子は退却の方針を社内に向けて発するも、世界の檜舞台で活躍することですっかり自信を付けた学卒者を中心とする若手社員の反対にあい、事業縮小の時機を逸してしまいます。金子はこのころから鈴木商店の統率力の欠如が顕著となり、このことが後年鈴木没落の第一の原因をなしたと語っています。(昭和金融恐慌秘話「鈴木王国の巻」[大阪朝日新聞社経済部編]より)
売上高で三井物産を凌駕するまでに成長した鈴木商店でしたが、この反動恐慌ともいうべき不況により受けた打撃は成長が急であっただけに甚大で、これを機に鈴木商店の業績は悪化の一途を辿り始めます。
大正9(1920)年10月7日、神戸製鋼所では5年間にわたる大工事の末に完成した神戸市脇浜の埋立地(海岸工場の敷地)において埋立工事の完工式が挙行されましたが、この頃には造船業界からの受注はばったり途絶え、「札かけ休業」状態での式典となりました。
金子はこの窮状を切り抜けるため、「八八艦隊」の建造(*)という海軍大拡張計画に伴う軍需に期待していました。
(*) 戦艦8隻・巡洋戦艦8隻の建造を主軸とし多数の巡洋艦・駆逐艦を建造するという大艦隊整備計画。建造費はわが国の国家予算レベルの莫大なものになる予定で、予算は大正9(1920)の議会で通っていました。アメリカ海軍が立てた新戦略「戦艦10隻・巡洋戦艦6隻」に対抗する計画であったことからこのように呼ばれました。
 しかし大戦後、日本はアメリカ、イギリスに次ぐ世界第3位の海軍力を誇示するようになったため日本に対する世界の警戒感は強まっており、そうした中、大正10(1921)年11月、ワシントンで開かれたイギリス、アメリカ、日本、フランスによる軍縮会議(ワシントン会議)で次の方針が決議されました。(左の写真はワシントン会議の総会議場に一堂に会した各国の全権団です)
しかし大戦後、日本はアメリカ、イギリスに次ぐ世界第3位の海軍力を誇示するようになったため日本に対する世界の警戒感は強まっており、そうした中、大正10(1921)年11月、ワシントンで開かれたイギリス、アメリカ、日本、フランスによる軍縮会議(ワシントン会議)で次の方針が決議されました。(左の写真はワシントン会議の総会議場に一堂に会した各国の全権団です)
(1)建艦競争を避け、国民の負担を軽減する。
(2)財政の窮迫を緩和し、文化的施設を促進する。
(3)戦争惹起の機会を減じ、世界の平和に貢献する。
翌大正11(1922)年2月、イギリス、アメリカ、日本、フランス、イタリアの間で海軍軍備制限条約が成立し、参加各国の間で艦船建造を制限することが決定します。この条約で主力艦(戦艦・巡戦艦)の合計基準排水量は、イギリスとアメリカがそれぞれ52万5,000㌧(比率5)、日本31万5,000㌧(同3)、フランスとイタリアがそれぞれ17万5,000㌧(同1.67)に制限され、航空母艦の合計基準排水量はイギリスとアメリカが13万5,000㌧、日本が8万1,000㌧、フランスとイタリアが6万㌧に制限されました。
 これに伴い日本海軍は建造済の「長門」、「陸奥」と航空母艦に転換された「赤城」、「加賀」のほかは建造中止を余儀なくされ、軍需に転換をはかりつつあった民間造船所および軍需関連企業の拡大方針はたちまち挫折します。
これに伴い日本海軍は建造済の「長門」、「陸奥」と航空母艦に転換された「赤城」、「加賀」のほかは建造中止を余儀なくされ、軍需に転換をはかりつつあった民間造船所および軍需関連企業の拡大方針はたちまち挫折します。
鈴木商店系列の企業も例外ではなく、金子の軍事拡張をあてにした起死回生策も不発に終わります。(左の写真は海軍軍備制限条約の結果を受け大正12年9月20日に除籍となり、大正13年1月19日、神戸製鋼所にて解体が終了した巡洋戦艦・鞍馬の廃艦作業中の様子です)
神戸製鋼所では八八艦隊計画に伴う需要増大に備えて大型機械の一貫製作を行う製鋼、鋳鋼、鍛鋼各工場を建設しましたが、一転400名の人員整理、民需への方向転換を余儀なくされます。同計画の中止は、当然に播磨造船所、鳥羽造船所にも大きな打撃を与え、ひいては鈴木商店に一大ショックを与えることとなりました。
金子は後に「大戦終結が本当に産業界に影響を与えたのは、大正7(1918)年11月の休戦条約でもなく、またベルサイユ講和条約でもなく、ワシントン軍縮会議だと思う」と語っています。(昭和金融恐慌秘話「鈴木王国の巻」より)
福沢桃介(福沢諭吉の女婿で明治・大正期の実業家)が自らの著書「財界人物我観」の中で、このことについて「百戦百勝の楚王項羽が、最後の一戦に敗れた如く、(ワシントン軍縮会議は)百雷の一斉落下、再び起つ能はざる大打撃を(鈴木商店に)与えた」と記しています。
この頃から鈴木商店は内包していた諸問題(企業統治能力の限界、資金の固定化、金利負担の増大など)が一気に顕在化しはじめ、破局への道を辿って行くことになります。
 当時、鈴木商店に対する台湾銀行の融資額は反動不況が本格化する第四代頭取・中川小十郎(左の写真)の副頭取時代の大正10(1921)年頃から加速度的に増大し、鈴木商店と台湾銀行は運命共同体ともいうべき二人三脚での歩みが進行して行きます。
当時、鈴木商店に対する台湾銀行の融資額は反動不況が本格化する第四代頭取・中川小十郎(左の写真)の副頭取時代の大正10(1921)年頃から加速度的に増大し、鈴木商店と台湾銀行は運命共同体ともいうべき二人三脚での歩みが進行して行きます。
台湾銀行は、日本による統治が本格的に始まる明治32(1899)年6月、台湾銀行法に基づき設置された半官半民の台湾の中央銀行(株式会社)で、紙幣発行権を持つ特殊銀行でありながら、商業銀行のほか為替銀行としての性格を有し、本来は内地資本の導入により台湾の産業を振興するとともに、対南方貿易の金融に便宜をはかることを主要業務としていました。(所謂「植民地銀行」)
唯一の鈴木商店系列である神戸の六十五銀行の規模は小さく、カネ辰・藤田商店の藤田助七が頭取を務めていた大正11(1922)年末、同時期の台湾銀行と比べると預金高で1.7%、貸出高で0.4%に過ぎず、とても鈴木商店を支えることができる規模ではありませんでした。
 鈴木商店と台湾銀行とのつながりは明治末期頃から金子と懇意となる台湾の初代民政長官・後藤新平を介して台湾の樟脳・砂糖を取り扱った関係から始まり、金子の旺盛な事業欲に応える形で当初は外国為替取引行として横浜正金銀行とともに取引が増加していきました。(左の写真は日本統治時代の建物が現在もそのまま使われている台湾銀行本店(台北市)です)
鈴木商店と台湾銀行とのつながりは明治末期頃から金子と懇意となる台湾の初代民政長官・後藤新平を介して台湾の樟脳・砂糖を取り扱った関係から始まり、金子の旺盛な事業欲に応える形で当初は外国為替取引行として横浜正金銀行とともに取引が増加していきました。(左の写真は日本統治時代の建物が現在もそのまま使われている台湾銀行本店(台北市)です)
台湾銀行としては商業銀行・外国為替銀行としての業務拡大を日本国内に求めるも、財閥系企業はすでに財閥銀行を擁しており同行の食い込む余地は見いだせず、財閥系以外の大手として躍進を続ける鈴木商店と結びつくのは当然の成り行きでした。
「生産こそ最も尊い行為」という金子直吉の経営哲学から他の財閥のように固有の銀行部門を持たなかった鈴木商店は直系・傍系の各関係会社の莫大な金融はすべて金子直吉の差配により万事借入金でまかなわれました。
これらの借入金は台湾銀行に大半を依存することとなり、大正10(1921)年からの同行の融資額は毎年4,000万円を超えるレベルにまで急増します。昭和元(1926)年末には同行の融資総額5億4,000万円の内、鈴木商店関係が5割をはるかに超えるという異常事態となります。このように鈴木商店の借入金は台湾銀行の金融力をはるかに超えるまでに増加し、両者の関係は抜き差しならない状況にまで発展してしまいます。
鈴木商店の莫大な借入金はその金利のためにさらに巨額の借入金を呼んで止まるところを知らず、その利払いだけでも総利益をつぎ込んでなお足りないという悪循環に陥ります。
 大正9(1920)年に高畑誠一、永井幸太郎とともに組織づくりの柱石であった支配人・西川文蔵(左の写真)が急逝したことは、鈴木商店の運命にとって致命的ともいうべき出来事でした。
大正9(1920)年に高畑誠一、永井幸太郎とともに組織づくりの柱石であった支配人・西川文蔵(左の写真)が急逝したことは、鈴木商店の運命にとって致命的ともいうべき出来事でした。
西川は高畑、永井らとともに資金を銀行からの借入だけに頼らず、株式を公開して広く外部に求めるという近代的な考え方を受け入れるようよう金子に進言しましたが、金子は鈴木商店は鈴木よねを筆頭とする鈴木家のものという思いが強く、骨身を削って得た利益は鈴木の利益として独占すべきで、株主に配当するぐらいならば借入をした方がましであるという信念を持っていたため、株式の公開や外部から経営に介入されることについては頑として首を縦に振りませんでした。
 以後、鈴木商店の組織・経営改革は台湾銀行の介入により進められることになります。大正11(1922)年、頭取・中川小十郎は元副頭取の監査役・下坂藤太郎(左の写真)を鈴木商店に送り込み、大正12(1923)年3月14日、鈴木商店は下坂の整理案により組織改革を断行します。
以後、鈴木商店の組織・経営改革は台湾銀行の介入により進められることになります。大正11(1922)年、頭取・中川小十郎は元副頭取の監査役・下坂藤太郎(左の写真)を鈴木商店に送り込み、大正12(1923)年3月14日、鈴木商店は下坂の整理案により組織改革を断行します。
すなわち、合名鈴木(合名会社鈴木商店)から貿易部門を分離して資本金8,000万円の株式鈴木(株式会社鈴木商店)とし、それまでの合名鈴木を資本金5,000万円の鈴木合名(鈴木合名会社)と改称し持ち株会社としました。
しかし、株式鈴木の重役陣はすべて鈴木の幹部で構成され、鈴木合名の責任社員・金子は、同時に株式鈴木の専務取締役の地位にあり旧体制から脱却したとは言い難く、経営の近代化からも程遠く、結局金子直吉の独断専行(ワンマン)体制が揺らぐことはありませんでした。
この後、鈴木商店の信用を大きく失墜させる問題が発生します。当時、鈴木商店と緊密な関係にあった日本製粉(*)は大戦後の反動不況による製粉市況の低迷に加え、慢性的な資金繰悪化により深刻な経営危機に陥り、鈴木商店と日本製粉は資金融通のため互いに融通手形を乱発する事態にまで至っていました。
(*)鈴木商店は大正9(1920)年に系列の札幌製粉、直営の大里製粉所を、大正14(1925)年には系列の東亜製粉を日本製粉と合併させ、日清製粉と並ぶ巨大製粉会社となった日本製粉の原料供給から販売までの権利を一手に握り、大株主として経営関与を強めていました。
 この難局を打開するため、金子直吉は日本製粉社長・岩崎清七(左の写真)と打開策を練り、日本製粉と日清製粉の合併を画策します。この合併話は、合併条件の決定を岩崎清七、日清製粉社長・正田貞一郎双方に関係が深い根津嘉一郎に無条件で委任することで話がまとまり、大正15(1926)年10月2日には合併の仮契約書まで交わされました。
この難局を打開するため、金子直吉は日本製粉社長・岩崎清七(左の写真)と打開策を練り、日本製粉と日清製粉の合併を画策します。この合併話は、合併条件の決定を岩崎清七、日清製粉社長・正田貞一郎双方に関係が深い根津嘉一郎に無条件で委任することで話がまとまり、大正15(1926)年10月2日には合併の仮契約書まで交わされました。
この業界1、2位の大型合併が実現すれば新会社は全国の製粉能力の約80%を占める大企業の誕生になり、業界の果てしない競争に終止符が打たれ、製粉業界に好結果をもたらすであろうとの期待がかけられました。
ところが、その後日清製粉と日本製粉の不良資産の査定額を巡り両社の意見が一致せず、同年10月18日になって日清側から合併を拒否する姿勢が示され、金子直吉の必死の工作も奏功せず、結局この合併契約は破談となってしまいます。
この合併が不調に終わると、日本製粉は同社の資金難を知った市中銀行からの借入がほぼ不可能となり、当面の支払資金を確保することも困難になりました。鈴木商店も年末を控えて多額の資金が必要となっていたため、金子と岩崎が奔走し大蔵大臣・片岡直温、日銀総裁・井上準之助に支援を求めた結果、台湾銀行を通じて日本製粉および鈴木商店へ各800万円、計1,600万円の救済融資が決定し、ようやく急場をしのぐことができました。
政府が救済に踏み切ったのは、日本製粉に万一のことがあれば鈴木商店も同様の運命を辿るであろうし、同時に鈴木商店の大口債権者である台湾銀行も窮地に立たされると懸念したからでした。
 結局、昭和2(1927)年1月17日、日清製粉との合併不調、日本製粉の経営悪化の責任を取り岩崎清七社長が辞任し、代わって鈴木商店東京支店長・窪田駒吉(左の写真)が同社社長に送り込まれ、日本製粉は資本金を4分の1に減資し経営刷新をはかりますが不調に終わり、その後三井物産の管理下に入ることになります。
結局、昭和2(1927)年1月17日、日清製粉との合併不調、日本製粉の経営悪化の責任を取り岩崎清七社長が辞任し、代わって鈴木商店東京支店長・窪田駒吉(左の写真)が同社社長に送り込まれ、日本製粉は資本金を4分の1に減資し経営刷新をはかりますが不調に終わり、その後三井物産の管理下に入ることになります。
この政府・日銀を巻き込んだ金融支援の過程においてそれまで世間に漏れることなく何とかやり繰りを続けていた鈴木商店の経営悪化が明るみとなり、鈴木商店の信用に極めて大きな影を落とすことになりました。
下記関連リンクの神戸新聞社・電子版「神戸新聞NEXT」から記事の一部をご覧下いただくことができます。