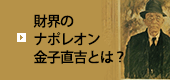神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の第31回「関東大震災の打撃」をご紹介します。
2017.1.30.
神戸新聞の連載「遙かな海路 巨大商社・鈴木商店が残したもの」の本編「第4部 荒波、そして(31) 関東大震災の打撃 「鈴木救済」政争の具に」が、1月29日(日)の神戸新聞に掲載されました。
今回の記事は、大正12(1923)年9月1日に東京、神奈川などを関東大震災が襲い、多大な犠牲が発生したことから始まります。続いて、金子直吉が山本権兵衛内閣の内務大臣・後藤新平に「モラトリアムノ件」と題した進言書を送ったこと、政府は直ちにモラトリアムを実施し、さらに震災手形損失補償令を公布したこと、しかし震災手形の回収は進まずその多くが台湾銀行(その大部分が鈴木商店関係)が占めていたこと、こうした中、片岡蔵相は「震災手形二法案」を議会に提出しますが、この法案が政争の具となったこと、そして激しい国会論戦の中での片岡の失言が、昭和金融恐慌の引き金を引いてしまったことなどが描かれています。
 わが国は第一次世界大戦の終結に伴う予想を超えた反動不況が続く中、不良債権を抱えた企業の整理やバブルで膨張した産業の合理化は一向に進まず、そこに追い打ちをかけるように大正12(1923)年9月1日午前11時58分、関東大震災が発生します。
わが国は第一次世界大戦の終結に伴う予想を超えた反動不況が続く中、不良債権を抱えた企業の整理やバブルで膨張した産業の合理化は一向に進まず、そこに追い打ちをかけるように大正12(1923)年9月1日午前11時58分、関東大震災が発生します。
大震災によって東京、神奈川を中心に死者・行方不明者は14万2,000人強に上り、全壊家屋13万戸、半壊家屋13万戸、焼失家屋46万4,900戸余、京浜地区の多くの企業、工場、住宅、銀行、商店は壊滅的な被害を受けました。(左は神奈川県庁と税関が消失する光景を描いた絵葉書です)
 大震災の発生により鈴木商店は巨額の損失を被り財務内容はいよいよ悪化します。大正12(1923)年末における株式鈴木(株式会社鈴木商店)と鈴木合名(鈴木合名会社)を合わせた損失は565万円を計上するに至り、資金繰りも極度に逼迫して鈴木の関係会社は互いに融通手形を乱発し合う混乱状態に陥ります。
大震災の発生により鈴木商店は巨額の損失を被り財務内容はいよいよ悪化します。大正12(1923)年末における株式鈴木(株式会社鈴木商店)と鈴木合名(鈴木合名会社)を合わせた損失は565万円を計上するに至り、資金繰りも極度に逼迫して鈴木の関係会社は互いに融通手形を乱発し合う混乱状態に陥ります。
 このころから、台湾銀行は鈴木商店の整理を本格的に検討します。頭取・森広蔵は大正12(1923)年10月、下坂藤太郎に替えて同行東京支店営業支配人であった佐々木義彦(左の写真)(佐々木は神戸高商で高畑誠一、永井幸太郎の1年先輩にあたり、後に神戸製鋼所、帝国人造絹糸、日商の監査役に就任)を鈴木商店に派遣し、大正13(1924)年3月には佐々木をヘッドにして森本準一、大西一三、平佐幹ほか3名を鈴木商店の神戸、大阪、東京支店に送り込み、それまでの監督的・間接的介入方針から一転して直接的管理へと踏み切りました。
このころから、台湾銀行は鈴木商店の整理を本格的に検討します。頭取・森広蔵は大正12(1923)年10月、下坂藤太郎に替えて同行東京支店営業支配人であった佐々木義彦(左の写真)(佐々木は神戸高商で高畑誠一、永井幸太郎の1年先輩にあたり、後に神戸製鋼所、帝国人造絹糸、日商の監査役に就任)を鈴木商店に派遣し、大正13(1924)年3月には佐々木をヘッドにして森本準一、大西一三、平佐幹ほか3名を鈴木商店の神戸、大阪、東京支店に送り込み、それまでの監督的・間接的介入方針から一転して直接的管理へと踏み切りました。
 すなわち、株式鈴木の経営は神戸高商の同期でもある高畑誠一(右の写真)と永井幸太郎のコンビに一任し、関係会社との金融も株式鈴木を中心にし、金子直吉はもっぱら鈴木合名の理事として関係会社の整理に注力することを骨子とした合理的な組織と計数に基づく近代的な経営管理体制の強行導入を目指しました。
すなわち、株式鈴木の経営は神戸高商の同期でもある高畑誠一(右の写真)と永井幸太郎のコンビに一任し、関係会社との金融も株式鈴木を中心にし、金子直吉はもっぱら鈴木合名の理事として関係会社の整理に注力することを骨子とした合理的な組織と計数に基づく近代的な経営管理体制の強行導入を目指しました。
大正15(1926)年2月、高畑はロンドンから15年ぶりに帰国し、永井とともに株式鈴木の取締役に任じられ、二人は佐々木のバックアップの下で鈴木商店の現状打開に向けての取組みを始めます。
台湾銀行は金子に対し株式鈴木からの退陣を強く迫りますが、このことを巡り社内において「土佐派」と「高商派」が激しく対立する中、金子は鈴木商店の本業「貿易部門」の株式鈴木に執着し、株式鈴木の副社長で、かつ鈴木合名の理事社員であった二代目・鈴木岩治郎はあくまでも金子を信頼し、金子と最後まで運命をともにする決断をするのでした。
当時、金子直吉の社内における地位はやはり絶大で、結局鈴木商店の体質改善には手がつけられないまま、しかも過剰借入の状態も改善されず、鈴木商店と台湾銀行の関係は互いに抜き差しならない共生関係にまで進展したまま、昭和2(1927)年の金融恐慌に突入していきます。
 「昭和金融恐慌史」(高橋亀吉著・森垣淑著)によれば、昭和金融恐慌は「三段階の波をもって来襲し、しかも次第にその波は高まり、最後の波により全国的な銀行パニックとなった」と記されています。第一期の波は昭和2(1927)年3月15日の渡辺銀行の休業に端を発した銀行取付けであり、第二期の波は同年3月28日に台湾銀行による鈴木商店への新規融資の停止を契機とする銀行取付けです。そして、第三期の波は同年4月18日の台湾銀行の休業を契機とする全国的な信用パニックであり、全国の銀行に預金取付けが一気に波及しました。
「昭和金融恐慌史」(高橋亀吉著・森垣淑著)によれば、昭和金融恐慌は「三段階の波をもって来襲し、しかも次第にその波は高まり、最後の波により全国的な銀行パニックとなった」と記されています。第一期の波は昭和2(1927)年3月15日の渡辺銀行の休業に端を発した銀行取付けであり、第二期の波は同年3月28日に台湾銀行による鈴木商店への新規融資の停止を契機とする銀行取付けです。そして、第三期の波は同年4月18日の台湾銀行の休業を契機とする全国的な信用パニックであり、全国の銀行に預金取付けが一気に波及しました。
関東大震災の発生により決済が困難になる手形は約21億円に上ると推定されました。大正12(1923)年9月7日、政府(山本権兵衛内閣)は支払猶予令(モラトリアム)を発令し、震災地域での手形の取立てや、決済を1カ月延期することを認めました。さらに9月27日、政府は「日銀震災手形割引損失補償令」により決済が最も困難な手形4億3,080万円について銀行がこの手形を持ち込むと日銀が再割引することとし、日銀が震災手形(*)で損失を被った場合、政府は1億円まで補償することとしました。
(*)震災手形とは、震災地(東京,神奈川,千葉,埼玉,静岡の各府県)を支払地とする手形、震災地で事業を営む者が振りだした手形、震災地で事業を営む者を支払人とする手形をいいました。
ところが、銀行や企業の中には大震災以前の不良債権を震災手形に紛れ込ませて日銀に持ち込むところもあるなどもあって震災手形の処理はなかなか進まず、2回にわたり前記「損失補償令」の期限延長が繰り返され、昭和2(1927)年1月1日時点では2億680万円の震災手形がなお未決済になっていました。
大震災後の不況は長期化し、体力の脆弱な銀行は次々に休業に追い込まれて行きました。政府や経済界は日本経済を立て直すためにはまず震災手形を処理し、金融を安定させることが不可欠との認識で一致します。そこで、政府(若槻礼次郎・憲政会内閣)は昭和元(1926)年の12月末日の通常議会に震災手形二法案(「震災手形善後処理法案」と「震災手形損失補償公債法案」)を提出します。
※震災手形二法案の議会提出の裏には政府が、当時急激に落ち込んでいた円為替相場の回復をはかるためには第一次世界大戦を機に禁止していた金輸出を解禁し、「金本位制」を復活する必要があると判断していたことがあり、その準備段階としてまず震災後の金融の大混乱を一掃することが必要との考えが根底にありました。大正15(1926)年9月、つとに早期金輸出解禁論者と目されていた片岡直温が大蔵大臣に就任しますが、この片岡の出現によって金輸出解禁が促進されたと見てもいいでしょう。
震災手形二法案の骨子は、この時点で未決済の震災手形を前記「損失補償令」による政府の負担1億円のほかに、新たに発行する公債1億700万円により救済しようというもので、台湾銀行などの銀行に政府が公債を貸し付けて資金繰りを支援し、鈴木商店など手形債務者は債務を10年間で返済するという内容でした。
鈴木商店は1億円に近い震災手形の当事者であったことから、金子直吉を中心にしてこの震災手形二法案が可決されるよう必死の政界工作を続けました。
 ところが、政友会(総裁・田中義一)と実業同志会(金子直吉の論敵であった鐘紡社長・武藤山治が結成)が与党・憲政会を執拗に攻撃する異様な状況下での震災手形二案審議の過程において、衆議院が暴露的な質問合戦の様相を呈して大混乱に陥る中、震災手形の未決済残高2億680万円のうち特殊銀行(台湾銀行、朝鮮銀行)分が5割を超す1億2,180万円を占め、そのほとんどが台湾銀行関係で、かつその大半の9,200万円が鈴木商店関係であること、しかも台湾銀行の融資総額の5割をはるかに超す3億7,800万円が鈴木商店関係で、しかもその大部分の3億2,200万円が不良債権化していることが明るみとなります。(左の写真は当時の台湾銀行神戸支店です)
ところが、政友会(総裁・田中義一)と実業同志会(金子直吉の論敵であった鐘紡社長・武藤山治が結成)が与党・憲政会を執拗に攻撃する異様な状況下での震災手形二案審議の過程において、衆議院が暴露的な質問合戦の様相を呈して大混乱に陥る中、震災手形の未決済残高2億680万円のうち特殊銀行(台湾銀行、朝鮮銀行)分が5割を超す1億2,180万円を占め、そのほとんどが台湾銀行関係で、かつその大半の9,200万円が鈴木商店関係であること、しかも台湾銀行の融資総額の5割をはるかに超す3億7,800万円が鈴木商店関係で、しかもその大部分の3億2,200万円が不良債権化していることが明るみとなります。(左の写真は当時の台湾銀行神戸支店です)
 結局この法案は一部の政商(鈴木商店)救済のための法案であるとされ、鈴木商店と憲政会の有力政治家で金子直吉と同郷の浜口雄幸(左の写真)や片岡直温との関係が糾弾されるなど政争の対象となってしまい、その後も衆議院・貴族院の両院において紛糾が続きました。
結局この法案は一部の政商(鈴木商店)救済のための法案であるとされ、鈴木商店と憲政会の有力政治家で金子直吉と同郷の浜口雄幸(左の写真)や片岡直温との関係が糾弾されるなど政争の対象となってしまい、その後も衆議院・貴族院の両院において紛糾が続きました。
昭和2(1927)年3月4日、前記の震災手形2法案は大混乱のうちにようやく衆議院を通過し貴族院に送られましたが同年3月14日、金融恐慌の第一波が訪れます。それは、混乱を極めていた衆議院予算総会(予算委員会)で大蔵大臣・片岡直温(左の写真)が野党の執拗な追求にあった際の歴史的失言(*)に端を発しました。
 (*)事務次官から渡されたメモを見た片岡は、東京の渡辺銀行が営業を続けていたにも関わらずまったく前ぶれもなく、「今日、正午ごろ渡辺銀行がとうとう破綻しました。誠に遺憾の事であります」と発言したもの。
(*)事務次官から渡されたメモを見た片岡は、東京の渡辺銀行が営業を続けていたにも関わらずまったく前ぶれもなく、「今日、正午ごろ渡辺銀行がとうとう破綻しました。誠に遺憾の事であります」と発言したもの。
翌3月15日には結局片岡の発言通り、東京の渡辺銀行と姉妹銀行のあかぢ貯蓄銀行が休業に追い込まれます。さらに3月19日から22日の間、中井銀行、八十四銀行、中沢銀行、村井銀行(以上東京)、左右田銀行(横浜)の5行が相次いで休業しました。
そして、東京近郊の小規模銀行も取付けに直面し、さらに関西に飛火していくつかの銀行に預金引出しが殺到しました。しかし、これはまだ金融恐慌の第一波にすぎませんでした。
下記関連リンクの神戸新聞社・電子版「神戸新聞NEXT」から記事の一部をご覧下いただくことができます。