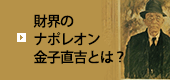鳥羽造船所電機工場(現・シンフォニアテクノロジー)の歴史②
鈴木商店が経営に乗り出した鳥羽造船所の一隅に電機試作工場が誕生
日露戦争終結後に到来した深刻な不況により鳥羽造船所は安田財閥からも見放され、三重紡績系列の四日市鉄工所に譲渡され事業の建て直しがはかられたが、もとより造船所の経営には不慣れなことから、廃業寸前の状況に陥り、やむなく地元の有志が神戸の鈴木商店に危機打開を懇請することとなった。
当時の鈴木商店は大正3(1914)年11月、同年7月の欧州における第一次世界大戦勃発に伴う商品価格の高騰を見越した大番頭・金子直吉がロンドン支店の高畑一誠一に「鉄と名の付くあらゆる商品」に対する一斉買いを指示すると、裁量の一切を任された高畑は鉄鋼、船舶、食料を始めとするあらゆる商品を買い進めることにより莫大な利益を上げ、さらに翌大正4(1915)年11月、金子がやはりロンドン支店の高畑誠一ら3名に宛てて鈴木商店の更なる大躍進を遂げていくにあたっての大号令とも言うべき気迫に満ちた、後に「天下三分の宣誓書」と称される書簡を発するなど、旭日の勢いで急成長を続けていた。
かねてより大戦による世界的な船腹不足と船価高騰を予想し、造船・海運事業の必要性を痛感していた金子直吉率いる鈴木商店は大正5(1916)年4月、兵庫県相生町長・唐端清太郎と地元有志の懇請により前途が絶望視されていた播磨造船株式会社の全事業を継承して株式会社播磨造船所を設立し、さらに同年10月には帝国汽船を設立。大正8(1919)年7月には金子の提案により9社・8船主からなる国策会社・国際汽船(現・商船三井)が設立された。
鳥羽造船所への鈴木商店の経営参加について、鳥羽町議会はすぐには衆議が一致しなかったが、養殖真珠の創始者として著名な御木本幸吉が"自分に任せてくれと"買って出た結果、伊勢山田出身の鈴木商店の松島誠の斡旋とも相まって町議も一決したので大正5(1916)年12月、鈴木商店は四日市鉄工所より造船業務と施設一切を継承して新たに「株式会社鳥羽造船所」を設立した。同社は、翌大正6(1917)年には中央鉄工所の電灯事業も引き継いで経営に乗り出した。
このとき真珠王・御木本幸吉は「天皇陛下にも下げたことのないアタマを金子(直吉)に下げたと言われるほど熱心であった」(鉄鋼新聞社編「鉄鋼巨人伝・田宮嘉右ヱ門」より)という。
株式会社鳥羽造船所は金子直吉から熱い信任を得ていた辻湊が取締役(工場主)に就任し、同社の経営の指揮を執ることになった。辻湊41歳の時であった。京都帝国大学機械工学科出身の生粋の技術者でありながら、むしろ事業家的手腕に天賦の才があった辻は、当時鈴木商店の造船部門のトップとして造船部長を務めており、播磨造船所の専務取締役も兼務していた。
辻は金子直吉の尖兵として活躍する一方、製糖、造船、電機、化学、石炭燃料、食品、放送など多岐にわたる産業界で、常に新しい挑戦を続けた先見性に富む希有な事業家でもあり、新分野・新技術に挑み続ける辻の精神は、今日までシンフォニアテクノロジーのDNAとなって継承され続けている。
辻が鳥羽の地で電気事業を興す決断をしたのは欧州で第一次世界大戦が勃発したことがきっかけであった。大戦は日本に未曾有の戦争景気をもたらした。特に海運業は輸出拡大と船舶不足により海上運賃が暴騰し、巨利を得た「船成金」が全国に続出するほどであった。
その頃には4,000トン級までの建造が可能となっていた鳥羽造船所でも、このような情勢を背景にして設備を拡張し従業員を増やしたが、それでも船舶の新造、修理に夜を日に継ぐほどの繁忙となった。
一方で、この造船部門の活況に伴い船舶用電機品の供給不足が深刻化し、設備を拡張するにも電気機器の入手確保は困難を極めていた。このような窮状下において、鳥羽造船所の指揮を執る辻はそれを逆手に取った大胆な打開策を打ち出す。それが「電気機器の自給化(内製化)計画」であった。
以前から電機事業の将来性に大きな夢を抱いていた辻は、船舶用電気機器および小形電気機器の専門メーカーとなることを思い描き、鳥羽の地に電機工場を建設し、電機事業の創業に着手した。
辻は電気技術者の招へいに東奔西走し、呉海軍工廠(広島県呉市)から電気技術の専門家で海軍機関少佐の大野弘を招へいすると、大野は呉海軍工廠から部下であった松岡政敏ほか数名の技術者を集めた。そして大正6(1917)年5月1日(*)、辻は鳥羽造船所の一隅に「電機試作工場」を設け、「電気係」を組織した。なお、この試作工場の面積はわずか100坪であったと伝えられている。
(*) この日がシンフォニアテクノロジーの創業日とされている。
辻が株式会社鳥羽造船所の設立から半年も経たないうちに電機工場の創設にまで一気に突き進んだのは、辻の妻の一族が関係していると思われる。辻の妻の父、中野宗宏はわが国初期の電気・通信系の技術官僚で、工部省権少技長を務めた。また、宗宏の弟で妻の叔父である中野初子は工部大学校(現・東京大学工学部)在学中に、わが国初のアーク灯の点灯実験に立ち会った5人のうちの一人で、後には東京帝国大学電気工学科の教授として後進の育成に尽力するなど、わが国初期の電気工学最大の功労者の一人である。
辻の妻の一族がわが国の電気・通信技術のパイオニアであったことが、起業センスに人一倍優れていた辻が電機事業に進出したことに大いに関係していたと言ってもいいだろう。
電機試作工場の創業当初においては、まず工場全体の電化用機器の製作を主とし、さらに新造船舶の発電機、配電盤をはじめ、船内の工事配線一切を電気係で施工する一方、一般用交流電動機(モータ)の標準型設計にも着手した。技術者たちはすこぶる意気軒昂であったが、何分にも一葉の図面もない新設の小工場のことであり、その苦労は並大抵ではなかった。
電機事業の発展を見るには何よりもまず技術陣の整備と強化が必要であると考えた辻の命により、大野は各方面の人物を物色した結果、京都帝国大学工学部電気学科を卒業し、当時関西では有数の企業であった奥村電機商会の設計課長を務めていた小田嶋修三に白羽の矢を立てた。
辻に面会した小田嶋は辻の人柄に敬愛の念を抱くところとなり、辻に内諾の旨を告げて一旦辞去したものの、奥村電機商会の社長は小田嶋の辞職をなかなか承諾せず、仲介者の尽力によりようやく辞職が認められた。大正6(1917)年10月14日、小田嶋は鳥羽に赴任し鳥羽造船所に入社する。小田嶋が初めて鳥羽を訪れたこの日は鈴木商店傘下となった鳥羽造船所で最初の起工となった紫尾山丸の進水式当日であった。
小田嶋は一旦京都に帰り、自身が講師として教えていた京都帝国大学付設の電気講習会の卒業生の中から優れた人材を数人選び、入社の承諾を得た。また、鈴木商店で採用されていた3人を加えて電機部門の陣容は著しく強化された。
一方、小田嶋を勧誘した大野は在職1年余りで退職し、小田嶋が電気係主任として技術を担当することになった。それから50年、小田嶋は80歳で在職(神鋼電機[シンフォニアテクノロジーの前身]の顧問役)のまま他界するまで、その生涯を鳥羽造船所発の電機工場の発展とともに歩むことになり、辻が"生みの親"と呼ばれるのに対し、小田嶋は"育ての親"と呼ばれている。