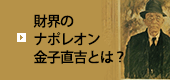鳥羽造船所電機工場(現・シンフォニアテクノロジー)の歴史⑩
日本経済に襲いかかる数々の荒波を乗り越え、会社の再建に傾注
昭和36(1961)年11月、会社再建の大任を全うした中井義雄が社長を退任し、代わって技術畑の専務取締役・冨満通哉(*)が神鋼電機の第3代社長に就任した。
(*)京都帝国大学電気工学科の鳥養利三郎教授(小田嶋修三と同学科の同期で、後・京都大学総長)の薫陶を受け、神戸製鋼所に入社。神戸製鋼所鳥羽製作工場時代から同工場に在籍し、神鋼電機の取締役、常務取締役、専務取締役を歴任した生粋の技術者。
冨満は世界トップレベルの技術を吸収した上で、それに同社の独自技術を融合させ、他の追随を許さない最高水準の製品で競争しようと目論んだ。その後しばらくの間不況が続いたが、昭和39(1964)年後半からいわゆる「いざなぎ景気」に突入する。この5年弱もの長期にわたる好景気は同社に規模の拡大を促し、昭和40(1965)年5月には豊橋工場の第1期工事が完了し、6月より操業を開始した。
伊勢工場、東京工場でも積極的な設備の拡張が行われ、鳥羽工場については近畿日本鉄道の路線延長(近鉄志摩線)や国道42号線の建設に協力するため一括売却し、昭和43(1968)年から昭和45(1970)年にかけて鳥羽市内の新用地(旧工場から西へ約2㎞離れた用地約75,370㎡で、旧鳥羽工場の1.4倍)に新工場が竣工し、生産設備はすべて新工場に移転された。ここに、旧鳥羽工場は明治11(1878)年に鳥羽城二の丸、三の丸跡地に鳥羽造船所として発祥して以来、90年におよぶ波乱に富んだ歴史の幕を下した。
昭和42(1967)年度下期には売上高が創業以来初の100億円台を記録した。昭和45(1970)年3月に大阪・千里丘陵で開催された日本万国博覧会では、お祭り広場のイベント用ロボットの自走台車、ロープウェイ用チケットの自動販売機、北大阪急行電鉄車両のエアブレーキ用コンプレッサモータなど同社の製品が大いに活躍した。
昭和43(1968)年10月1日、同社育ての親である小田嶋修三が顧問役のままで死去した。(享年80歳) 小田嶋は30歳の時、同社生みの親である創業者の辻湊の招へいを受け、大正6(1917)年10月に鳥羽造船所に入社し、電気係に着任して以来半世紀、「他と異なった特色ある技術・製品で生きるべき」という基本方針の下で大いに社業を発展させた。小田嶋の歩みはまさに同社の歴史そのものと言っても過言ではない。
ニクソンショック(ドルショック)により日本経済が不況に突入した昭和46(1971)年8月、10年の長きにわたって安定した経営を続けてきた冨満が社長を退任し、第一銀行の出身で神戸製鋼所常務取締役から同社の会長に就任していた湊静男が第4代社長に就任した。
湊は神鋼グループとの連携強化により「システムパワーの神鋼電機」として脱重電を打ち出し、プラント事業の拡大およびレジャー・不動産部門を中心とした相次ぐ関係会社の設立に注力した。しかし、ボウリング場をはじめとする多角化をはかった関係会社の業績は、一部を除いて予期した成果を挙げることができず、また本業の業績も思うにまかせない状態が続いた。
その後、ニクソンショックの影響に加え、昭和48(1973)年10月の第4次中東戦争に端を発する第1次オイルショックの襲来により、日本経済が高度成長期の終焉を迎えると、同時に同社は大幅な損失を計上し深刻な経営難に陥った。中井が再建を果たし、冨満によって著しい発展を見た同社の経営基盤は、湊の志とは裏腹にもろくも崩れ去った。
昭和52(1977)年6月、湊静男に代わって西川廣が神戸製鋼所常務取締役から転身し、第5代社長に就任した。西川の社長就任は、文字通り危急存亡にあった同社の経営危機を打開する大役を任されての登場であった。同年10月、文字通り同社の命運を託した再建計画(受注拡大、生産能率の向上、経営組織の改善、子会社の整理促進などが柱)が労組との厳しい協議の上で発表され、東京工場およびその他の遊休不動産の売却、1,1184人の人員整理などの対策が厳格に進められた。
昭和53(1978)年10月、豊橋工場内に振動機工場が完成したことに伴い、前記再建計画に沿って、昭和18(1943)年10月に神戸製鋼所東京研究所として開設された東京工場が閉鎖された。
途中、昭和53(1978)年12月のイラン革命に端を発する第2次オイルショックが起こったものの、鉄鋼業界、機械業界などの省エネ、省人化といった合理化を目的とした民間設備投資関連需要が活発に推移するとともに、官公庁向け上下水道電気設備や船舶用電装品、海外市場向け発電設備などの設備需要の増加などが業績回復に貢献し、同社の再建計画は順調に進行した。
西川が社長に就任した昭和52(1977)年の年度末に97億円に膨れ上がっていた累積損失は、昭和56(1981)年度にはついに19億円となり累積損失の解消は目前に迫った。しかし、当局による金融引き締めに伴い昭和56(1981)年度から不況が到来すると、昭和57(1982)年度には4年間続いた経常黒字から再び赤字へと転落した。
昭和58(1983)年6月、累積損失の解消に一定の成果を挙げた西川が社長を退任し、代わって冨満通哉以来久方ぶりの技術畑出身の猪股茂男が神戸製鋼所専務取締役から転身し、第6代社長に就任した。
猪股は積極的・攻撃的経営に転換することにより再建を達成しようとしたが、昭和60(1985)年9月22日の「プラザ合意」による急激な円高の進行に伴う設備投資の縮小により売上高が激減し、資産売却や増資により存続の危機からは逃れることができたものの、累積損失の一掃という最終目標は断念せざるを得なかった。
ところが、「プラザ合意」以降に超金融緩和による急激な内需拡大策が執られたわが国は、いわゆる「バブル経済」に突入し、同社の業績は地道な努力と相まって急速に回復し始めた。これにより累積損失解消の目途を立てた猪股は退任を決意し平成元(1989)年6月、鈴木昭男が神戸製鋼所専務取締役から転身し、第7代社長に就任した。
当時、バブル経済は絶頂期を迎えており、同社にも強烈な追い風となって、平成元(1989)年度には10数年来の懸案であった累積損失が遂に一掃された。鈴木は「グッド・コミュニケーション」による社内風土の改革を掲げつつ、航空機、宇宙、半導体、情報機器を中心に販路の拡大を進め、平成3(1991)年度には同社が長年目標としてきた売上高1,000億円を達成した。しかし、この期は同社の企業体質の強化が道半ばであることの裏返しとして、増収減益であった。
平成2(1990)年3月、大蔵省が金融機関にいわゆる貸出の「総量規制」を通知すると、これをきっかけにバブル経済はもろくも崩壊し、不況に弱い企業体質の同社にも不況の波が襲いかかった。同社はあらゆる対策を講じたが不況はますます猛威を振るい、平成5(1993)年度には昭和62(1987)年度から続いていた経常黒字が途絶え、一転して赤字を計上し無配に転落した。