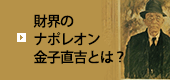大日本塩業(現・日塩)の歩み③
大日本塩業が鈴木商店の傘下に入る
鈴木商店は早くから専売事業とは密接なつながりがあった。初代大蔵省専売局長官・仁尾惟茂(高知県中村市出身)と第二代長官・浜口雄幸(高知市出身)が金子直吉と同じ土佐出身という人脈面、また事業面では、台湾において台湾総督府民政長官・後藤新平が提唱した樟脳専売制度の導入を金子直吉が支持し、反対陣営を切り崩して同制度の実現に至った(明治32年)ことが評価され、鈴木商店は台湾の専売樟脳油の65%の販売権を獲得し、このことが後の鈴木商店大躍進の契機となったことがあげられる。
鈴木商店の塩業への進出は台湾専売塩の内地(日本国内)への移出販売の請負が起点となり、塩業界に地位を築いていった。後藤新平は、明治28(1895)年以降完全自由販売となっていた台湾塩の販売について、塩価の安定、塩業収益の財源化等を目的として明治32(1899)年に塩専売制度を実施した。
台湾の塩専売制度は実施から3年後には安定した制度となり、内地塩以上に品質の良い製品が生産できるようになり、それまで食塩の輸入地であった台湾は一転して輸出地となり、内地で不足していた食塩を補う重要な移出地となった。
明治40(1907)年、台湾専売塩の移出販売を請負っていた愛知県知多郡半田町(現・半田市)の豪商・(二代目)小栗富治郎 (*)が経営する小栗銀行(名古屋市)は、日露戦争終結後の「明治四十年恐慌」とも呼ばれている恐慌に巻き込まれた結果、同年6月に休業・経営破綻し、これを機に小栗家は没落の一途を辿った。
(*)弘化年間(江戸後期)以降に半田村で酒造業、海運業を営んでいた(初代)小栗富治郎の事業を引き継いだ(二代目)小栗富治郎は、明治25(1892)年に醤油醸造業を開始し、その後亀崎銀行の設立、精米場の開設、知多紡績の設立、台湾・中国・北海道等との汽船航路の開設など経営多角化を本格化した。小栗の経営広域化の象徴が明治31(1898)年の小栗銀行設立であった。翌明治32(1899)年には台湾塩の内地における一手販売権を獲得し、明治36(1903)年には半田に製塩工場を設立した。明治39(1906)年、小栗は貴族院議員に当選する。
小栗銀行の経営破綻に伴う整理は難航し、鈴木商店の金子直吉は桂太郎(第11代、第13代、第15代総理大臣)から相談を受けた。
金子は桂の求めに応じ、鈴木商店は小栗富治郎が保有していた台湾塩の一手販売権を継承し、この一手販売権を手掛かりにして小栗銀行の整理に着手するとともに、台湾塩の内地への移出業務を担うこととなり明治42(1909)年、その受け皿として「東洋塩業」(明治43年、社名を「台湾塩業」に変更)を設立した。そして、東洋塩業の株式を同行の預金者に配分するという手法で預金者の保護をはかりつつ、同行の整理を進めた。
鈴木商店が台湾塩の内地への移出業務に携わるようになった経緯については「金子直吉伝」に次のように記されているが、鈴木商店は塩の安値安定供給に強いこだわりを持っていた金子の「塩を制する者は化学工業の経営を制する。即ちソーダ加里は多数の工業を制約する」という強い信念の下、塩業へ進出していった。
「我国の塩は外国に比べて高い。日本の塩の生産費は世界各国と比べて驚くべき高率である。金子は安い良い塩を沢山造って一般に供給することは事業家として国家に尽す所以であるということに着眼した。折しも名古屋にあった小栗銀行の整理が難航し、桂太郎より相談を受けた金子は『台湾から内地へ塩を送る権利を貰いたい。そうすればそれを手掛かりにして私は整理をやります』と答えた。
桂公は『それは安い事だ。それでは台湾から塩を持って来る権利(台湾塩の一手販売権)を君にやるから、それで整理をつけてくれ』と頼んだ。そこで、金子は(この一手販売権を基礎にした)東洋塩業(後・台湾塩業)を創立し、その株式を小栗銀行の預金者に配分するという手法で預金者を保護しつつ整理を断行した。」
小栗家・小栗銀行の整理を始めとする一連の困難を克服するため、金子が白羽の矢を立てたのが藤田謙一であった。藤田は大蔵省専売局より煙草を扱う岩谷商会に入り、事業家としての基礎を築いた。
藤田は金子の要請を受けて鈴木商店に入り、東洋塩業の取締役に就任すると、持ち前の経営手腕を発揮し、金子をもってしても難航していた小栗銀行の整理を完遂して東洋塩業の経営を軌道に乗せると、社長の桂二郎(桂太郎の実弟)の下で同社の専務取締役に就任した。
金子の信頼を得た藤田は大正5(1916)年12月に大日本塩業の社長に就任し(大正7年11月に辞任)、さらに、その後は鈴木商店の経営参謀として、また関係会社の役員として活躍することになる。
東洋塩業は創立時より台湾塩の内地への移出販売に邁進したが、金子の思惑に反して内地での販路は思うようには伸びなかった。その理由は、明治39(1906)年以来日本に輸入されていた関東州塩が内地市場を席捲していたことにあった。
当時内地市場では大日本塩業が先行して関東州塩の販路拡張を積極的にはかっており、鈴木商店は同社の販売網に阻まれて出鼻をくじかれ、苦戦を強いられたのであった。
そこで、金子は関東州において塩田経営を掌握し、かつ関東州塩の内地における一手販売権を握る大日本塩業との間に販売協定を締結し、さらに一手販売権を譲渡するよう同社に申し入れた。しかし、大日本塩業はこれを拒否した。
明治43(1910)年、満漢塩業の全株式2万株が市場に放出された。満漢塩業の関東州における塩田開設権は5,500町歩で、大日本塩業の4,000町歩を上回っており、もしこの株式が鈴木商店に渡ると将来強力な競争相手になるのは必至とみた大日本塩業は、資金的な余裕がなかったため関西随一の株成金であった島徳蔵に依頼して同社株式の買占めを依頼した。同じ年の明治43(1910)年、東洋塩業は社名を「台湾塩業」に変更した。
しかし、大日本塩業は鈴木商店の進出を阻止することはできなかった。満漢塩業は、当初同社が普蘭店・三十里堡間の1,000町歩の塩田開設許可を受けていたにもかかわらず、明治45(1912)年に至っても未着手のため許可を取り消されることになり、かわって鈴木商店がこの開設権を取得し、関東州での製塩業の足掛かりを得ることとなった。なお、鈴木商店は大正4(1915)年に「東亜塩業」を設立し、同社にこの開設権を譲渡している。
さらに、前記の島徳蔵は満漢塩業の株式を買占めた後の明治45(1912)年7月に大日本塩業の社長に就任していたが大正3(1914)年、その島が大日本塩業の株式の過半数を鈴木商店に売り渡すという事態が起こった。島が鈴木商店に同社の株式を売却した経緯・理由は定かではないが、島が製塩業の将来に見切りをつけたため、とも推測される。
これにより、金子直吉のかねてからの望みが実現し、鈴木商店は台湾塩の移入販売を一手に行う台湾塩業に加えて、関東州における塩田経営を掌握し、関東州塩の輸入販売を一手に行う大日本塩業の実権を掌中に収めることとなった。
鈴木商店はしばらく大日本塩業と台湾塩業の2社を兼営したが、大正6(1917)年12月に台湾塩業を大日本塩業に合併した。なお、大日本塩業は大正4(1915)年1月に満漢塩業を、同年8月に東亜塩業(鈴木商店系列)を、大正5(1916)年に村井文太の事業を合併している。
鈴木商店は日本国内でも再製塩工場の設立を進めた。まず明治43(1910)年、北九州・大里に直営の再製塩工場を設立し、関東州塩、台湾塩を再製して国内、ロシア領沿海州、香港等に販路を拡げていった。さらに大正7(1918)年、下関・彦島の日本金属彦島製錬所内に分工場として精錬所の余熱を利用した再製塩工場を建設した。