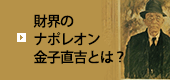大日本塩業(現・日塩)の歩み④
親会社・鈴木商店の経営破綻により会社存亡の危機に直面
第一次世界大戦の勃発は各種ソーダ工業製品のヨーロッパからの輸入の減少あるいは途絶を招き、このことが日本国内で塩を大量に必要とするソーダ工業の勃興を促した。
ソーダ工業で使用する原料塩については特別価格が定められ、台湾塩や関東州塩を安価に供給する法策がとられていた。それでもなお原料塩の価格は高く、ようやく端緒を開いたソーダ工業の発展を阻害する恐れがあったため、一部メーカーから大蔵省専売局に申請がなされた結果大正6(1917)年10月、ソーダ事業者による自己輸入が実現した。
このソーダ工業用塩に関する「自己輸入制度」は塩専売制度の実質的な後退を意味するものであり、これ以降、割高な国内塩は一般用塩の分野に封じ込められ、同時にソーダ事業者は専売制度の下でも、自らのリスクにおいて原料塩を調達できるようになった。
前記のとおり、関東州の日本人による塩田経営は大正初期には大日本塩業の一手に帰したが大正3(1914)年11月、第一次世界大戦に参戦した日本が中国の青島を占領し、それまでドイツが保持していた膠州湾(青島)租借地の権益を継承すると、大正7(1918)年の内地塩の大凶作を機に日本人が青島の塩田経営に殺到した。(*)
(*)大日本塩業も膠州湾内の水深が浅く干満潮の差が大きいこと、かつ降雨が少ない点に着目し、大正8(1919)年に青島の海庄で塩田の開発に着手。大正10(1921)年までに429町歩の塩田を完成させている。
これにより青島塩が内地(日本国内)や朝鮮に輸出され始めると、関東州塩の販売は"青島塩"という強力な競争相手の出現により容易ならざる事態となった。
このため関東州ではその後の情勢の見通しについて苦慮する時期が続き、大正6(1917)年~大正8(1919)年の間は新たな塩田開発は行われず、同社も既存の塩田による生産と輸出の増進に専念していた。一方で、大正7(1918)年の内地塩の大凶作が契機となって東洋拓殖、東洋捕鯨、満州殖産の3社と個人3名が関東州の塩田経営に加わった。
ところが大正11(1922)年2月、ワシントン会議の結果、日本と中国政府との間で「山東懸案解決に関する条約」が締結されると膠州湾(青島)の権益は中国に返還され、日本人が開設した塩田は中国政府によって買収された。
これにより青島塩の輸出は途絶え、その補充のため一転して関東州塩の需要が増加した。(その後、大正15年2月に「青島塩輸出に関する細目協定」が成立し、青島塩の輸出は再開される。)
塩田増設の機運が高まった関東州では、大正13(1924)年には各地で合計812町歩の塩田が竣工したが、同社は関東州内の主要な産地に出張所を設置し、引き続き州内の塩田の過半を占める大規模な塩田経営を行い、自己製塩のほかにも中国人製塩業者からの買付けを行うなど確固たる地歩を築いていった。
大正13年度末の関東州における大日本塩業の塩田面積、原塩生産高は次のとおり圧倒的なシェアを占めた。
・塩田面積 ・・・・ 3,838町歩で、全体の66%(日本人経営の塩田に限れば90%)を占めた。
・原塩生産高 ・・・・ 141,499トンで、全体の56%(日本人経営の塩田に限れば94%)を占めた。
一方で大正6(1917)年、同社は鈴木商店系列の「台湾塩業」(明治43年、東洋塩業から社名を変更)を合併し、これにより台湾塩についても「移入取扱人」に指定された。
関東州で生産される塩は結晶が粗大で不整形である(こぶし大のものも混じっていた)上に、砂や粘土を含んで色相も良くなかった。このため、不純物を除去して純度を高めるには粉砕洗滌によるか、水・海水・鹹水などで溶解・濾過した後に溶液を煎熬(煮つめること)することにより塩を再製加工する必要があった。
※関東州の塩を大別すると天日原塩、煎熬塩の2種類になる。天日原塩は加工されて洗滌原塩(天日原塩をそのまま洗滌したもの)、洗滌塩(天日原塩を洗滌した後粉砕し、さらに洗滌したもの)、粉砕洗滌塩(洗滌塩をふるい分けし、さらに洗滌したもの)の3種類になり、煎熬塩は再製塩(天日原塩を海水・鹹水などに溶解し、濾過後の溶液を煎熬し生成したもの)、鹹水煎熬塩(塩田で生成された鹹水、あるいは塩田苦汁を火力で濃縮して塩を抽出したもの)の2種類に分類される。
大日本塩業は大正2(1913)年に関東州の双島湾と普蘭店に再製塩工場を、大正3(1914)年には貔子窩管内の大長山島に粉砕工場を建設して内地専売局、朝鮮、ロシア領沿海州などへ輸出した。一方、内地では大正5(1616)年~大正7(1918)年の塩の凶作を補うため、大正7(1918)年に山口県・彦島に、大正8(1919)年には横浜に粉砕洗滌工場を建設して操業を開始した。これが日本国内における粉砕塩生産の嚆矢と言われている。
その直後、塩の再製加工の方式が大蔵省専売局から原料塩を受け取って加工を請け負う方式に変更されたことから、同社は大正8(1919)年より大正10(1921)年頃まで、彦島、横浜の両工場において専売局からの受託業務として粉砕塩および粉砕洗滌塩の加工を行った。
同社が関東州塩および台湾塩の「輸移入取扱人」および「特別元売捌人」に指定されたことは前記の通りであるが、その後の日本の化学工業の発展や国内塩の不足により大正6(1917)年12月、同社は関東州塩、台湾塩のみならず青島塩、ジャワ塩、スペイン塩、エジプト塩、ドイツ塩等の外塩の輸入において特別元売捌人の指定を受け、さらには官費回送の開始に伴って保管、回送と回送先での販売、それに付帯する発送元倉庫での包装作業について一括して大蔵省専売局より下命を受けた。
大正8(1919)年に入ると、前年の内地塩の大凶作により輸移入塩の需要が増加し、輸移入塩について特別元売捌人である同社が介在しない販売を求める要望が高まった。大蔵省専売局はこれを受け入れ、同局がいったん買い取った後に広く一般塩元売捌人に売り渡すこととなった(輸移入塩の一手販売の撤廃)ため同社の介在する余地がなくなり同年4月、同社は輸移入塩に関する「特別元売捌人」の指定を返上した。
その見返りとして、輸移入塩についても官費回送が行われるようになり大正8年(1919)年5月、この輸移入塩の官費回送については、実状に即して大阪地方専売局の管轄区域以東は同社が、以西は日本食塩回送(株)が取り扱うことになった。また輸移入塩の一手販売の撤廃に伴い、同社は一般用塩の販売を中止し、漁業用塩のみの販売に専念する方針に転換をはかった。
それまで、同社は各地に倉庫を建設して官塩の貯蔵に使用してきたが、大正12(1923)年の関東大震災で深川の倉庫(600坪)を焼失したため、その後この倉庫を復旧するとともに東京・芝浦月見町にアメリカ式の最新鉄骨組立倉庫800坪、東京・深川区東扇橋町に800坪、深川区富川町に400坪、横浜市千若町に400坪の木造倉庫の新築と増築を実施した。
これに伴い、同社は官塩と葉たばこの保管を引受け大正13(1924)年8月、定款の目的に「船舶業ならびに倉庫業」を加えて一般貨物の倉庫業務を開始した。また、同社は大正12(1923)年以降10艘を超える船舶を購入し、塩輸送のほか一般貨物の輸送も開始した。
大日本塩業の親会社であった鈴木商店は、大正中期には貿易年商において三井物産を凌駕するまでに成長したが、第一次世界大戦の終結に伴う反動恐慌ともいうべき不況により受けた打撃は、その成長が急であっただけに甚大で、さらに関東大震災による打撃も加わり、鈴木商店の業績は悪化の一途をたどった。
そして、関東大震災の発生に伴い決済不能となった震災手形を救済することを目的とした「震災手形二法案」(「震災手形善後処理法案」と「震災手形損失補償公債法案」)の法案審議の最中に発生したいわゆる「昭和金融恐慌」に翻弄されつつ昭和2(1927)年4月2日、主力銀行・台湾銀行から融資打切りの最後通告を受けた鈴木商店は経営破綻を余儀なくされた。
大正3(1914)年に満漢塩業の株式買占めを機に大日本塩業の社長に就任していた島徳三が同社の過半数を鈴木商店に売り渡すという事態が起こったことは前記のとおりであるが、それ以来、同社は株式を持ち合う形で鈴木商店の子会社の立場にあったため、鈴木商店が経営破綻に至ったことで大打撃を受け、会社存亡の危機に直面することとなった。
しかし、幸いにも2つの懸案事項が有利に解決したことで窮地を脱することができた。その1つは、船舶の売却で、台湾銀行の好意により同社所有の船舶を摂津商船と山下汽船に有利な価格で売却することにより債務を弁済できたこと。その2は、横浜千若町の土地取得について、浪華倉庫から仮登記抹消の訴訟を起こされており、鈴木商店の手形と絡んで問題が複雑になっていたところ、その手形の債権者である台湾銀行の寛大な措置により無事に決着したことであった。
とはいえ、鈴木商店が保有していた大日本塩業の株式は横浜正金銀行、台湾銀行などが肩代わりすることとなり、昭和2(1927)年8月31日の株主総会、同年9月21日の株主総会延会、同日の臨時株主総会により狩野藏次郎社長ほか大半の役員が退任した。
これに伴い、同社は横浜正金銀行の管理下に置かれ昭和2(1927)年9月、同行の一宮鈴太郎副頭取の弟である一宮銀生(三井物産出身)が代表取締役に就任し(*)、同時に入社した三井物産出身者が会社の要所に配置され、それまでの前垂れ掛商法から物産式の積極商法へと転換をはかることとなった。
(*)昭和11(1936)年8月、一宮銀生は同社の社長に就任する。