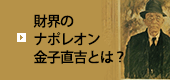大日本塩業(現・日塩)の歩み⑤
戦時体制下での工業用塩安定確保のため、外地での塩田拡張を強力に推進
大正15(1926)年2月、「青島塩輸出に関する細目協定」が成立すると青島塩の輸出が再開され、さらに内地塩の豊作に加えてエジプト塩、ベルギー塩、ドイツ塩などが市場へ進出したことにより、関東州塩は輸出が減少し、一転して生産過剰に陥った。
大日本塩業は一般食用塩のほかに工業用塩、漁業用塩の需要を開拓してこの難局を乗り切ろうとしたが、関東州塩は天日塩であるため結晶が粗大・不整形で砂や粘土の混入が多く、色相も良くなかったため漁業用、工業用いずれにも不適で原塩のままでは販売できず、しかも価格において青島塩に及ばなかった。
そこで、同社は品質向上と廉価供給を目指して鋭意実験を重ねた結果、ついに青島塩よりも純度において約3%優れた産塩を供給できるようになった。これが市場奪回の糸口となり、同社は昭和6(1931)年頃から関東州の貔子窩、双島湾、営城子、普蘭店、三道湾、五島に加工塩工場を建設して本格的な粉砕加工を開始し、洗滌塩、洗滌原塩、粉砕洗滌塩を生産した。
双島湾の加工塩工場で生産した塩化ナトリウムの含有率96%の粉砕洗滌塩は漁業用塩として業界の要望に合致し、北洋漁業用塩市場において力強い進出を実現した。また、この粉砕洗滌塩は内地の工業用塩市場においても、品質において十分外国塩と拮抗しうる製品として急速に需要を喚起していった。
昭和初期の日本はソーダ灰、苛性ソーダを使用する人絹、ガラス、石鹸、製紙、染料などのソーダ工業が急成長期に入り、原料塩の需要が増大して関東州塩、台湾塩、青島塩をもってしても充足できず、外国塩を輸入しなければ需給の均衡がとれない状況にあった。大蔵省専売局は過去に関東州塩、台湾塩の供給過剰に苦慮したことから、利用者であるメーカー側の意図もあり、この不足分については遠海塩(*)に頼ることを決定した。
(*)遠海塩は、西はマラッカ海峡以西のインド地区、紅海地区、地中海地区、イギリス、ドイツ等、東はアメリカ、メキシコ、西インド諸島等の遠距離から輸入される塩をいう。
同社は、昭和2(1927)年9月以降、一宮銀生代表取締役を中心とする三井物産出身者による新体制の下で、前記のとおり関東州塩の品質改善に努める一方で、昭和6(1931)年から三菱商事、三井物産、岩井商店などと連携し、日商ロンドン支店やMOXEY-SAVONを通じてエジプト塩を一手に扱い、そのほかジプチ塩、エチオピアのマツサワ(現・エチオピア) 塩の取り扱いにも参画した。準近海塩では、昭和8(1933)年から仏印(現・ベトナム)塩、ジャワ(現・インドネシア)塩も取り扱い、工業用や漁業用の内地需要に対応した。
同社は、前記のとおり鈴木商店が経営破綻した昭和2(1927)年に横浜正金銀行の管理下に置かれたが昭和9(1934)年、太陽曹達(鈴木商店を源流とする天然ソーダの輸入販売会社、後・太陽産業、現・太陽鉱工)と日商(後・日商岩井、現・双日)が横浜正金銀行から同社株を取得し(*)、両社による同社の持株比率は50.4%に達した。
(*) 横浜正金銀行が保有していた大日本塩業株40,330株のうち太陽曹達が20,330株、日商が20,000株を取得した。
なお、同社経営の屋台骨を支える関東州の塩田(東老灘、夾心子、普蘭店、双島湾を始めとする9カ所)の面積は、昭和10(1935)年末では5,723町歩となり、工事中のものを含めると7,000町歩にまで達した。(昭和元年12月末の塩田面積は4,200町歩余りであった。)
当時の日本は、昭和6(1931)年の満州事変、昭和12(1937)年の日華事変を経て太平洋戦争へと突き進んでいく途上にあった。昭和13(1938)年には国民総動員法が成立し国民は耐乏生活を強いられ、経済統制を始めとする戦時体制が強化されていった。
国際情勢が緊迫の度を加えていくに従って、日本国内では工業用塩の安定確保が喫緊の課題となり、昭和11(1936)年には「近海塩増産5カ年計画」が立てられ、工業用塩の主要な供給源に対する方針が、それまでの「遠主近従」(近海塩の不足を遠海塩で補充する)から「近主遠従」(遠海塩の不足を近海塩で補充する)へと大転換された。そして、各地域別の目標が定められ新規塩田の開発、塩業会社の設立などが一斉に実施された。
国家的使命が一段と高まった同社は、関東州の普蘭店、貔子窩、双島湾などでさらなる塩田拡張を強力に推進した。その結果、昭和14(1939)年末には塩田面積7,288町歩、未完成塩田面積2,241町歩となり、総面積で1万町歩に手が届くところまで開発が進んだ。
さらに、同社は台湾、朝鮮での塩田の新設を開始した。昭和12(1937)年3月、同社は岡山県児島郡の著名な塩田主・野崎武吉郎が台湾西南海岸に面した布袋で開発した島内随一の優良塩田142町歩を譲り受け、台湾の塩田を初めて所有した。台湾の製塩事業の中心地は主として西南海岸で、製塩方式は関東州や朝鮮と同様の天日製塩であった。
なお、台湾の内地向け工業用塩の積込業務は同社の安平出張所(昭和17年に支店に昇格)が一手に請け負っていたが昭和19(1944)年2月、これを発展的に解消して塩荷役を専門に取り扱う台湾塩荷役(株)を南日本塩業、台湾製塩とともに設立した。
朝鮮は外地の優良な産地に比べると地理上、気象上の条件は必ずしも良くなかったものの、塩田に相応しい広大な適地を保有しており、製塩技術の進歩により急速にその欠点を克服していった。昭和13(1927)年、同社は平安南道の清川江沿岸の干拓地1,118町歩を確保し、天日塩田の築造工事を開始した。
前記のとおり、輸移入塩の官費回送については、大正8年(1919)年5月以降は大阪地方専売局の管轄区域以東は同社が、以西は日本食塩回送が取扱ってきたが、日中戦争が勃発し戦時体制に入ると統制を強化する国策の一環として昭和14(1939)年9月、事業の統合・整理の観点から一元的に日本食塩回送が取扱うことになった。
これにより大日本塩業は回送業務を日本食塩回送に移譲した。ただし、東京、横浜、半田の各港の輸移入塩回送は請負形式により、実態としては引き続き同社が行うこととなり、地方代理店扱いの回送業務についても大日本塩業代理店の契約条件はそのまま継続された。
これに先立ち、昭和12(1937)年に「小運送業法」が施行されると、同社は両国、亀戸、平井、小名木川(以上、東京)、千若信号場、海神奈川、東高島の各駅(以上、横浜)、名古屋港駅において小運送業者の免許を取得し、清水、直江津、新潟、塩釜などでは代理店に各駅での免許を取得させた。
昭和12(1937)年6月、近海塩の増産には塩業各社相互の緊密な連携と協調が必須であることから、専売局の強い要望もあって大日本塩業、東洋殖拓、同和塩業、満州塩業等7社からなる「近海塩業会」が設立され、会長には大日本塩業の島本正一社長が就任し、事務所も大日本塩業内に置かれた。この近海塩業会は、後に太平洋戦争の戦局が苛烈を極めるようになると、大陸中継輸送などで近海塩業関係者の豊富な知識と経験が生かされ、大活躍することになる。
当時の日本はソーダ工業の躍進に伴い、外国塩の供給源については遠海塩、準近海塩と広範囲にわたるようになっていたが、日本の商社はそれぞれ独自に輸入するだけで統制がとれておらず、その状態が続くと外国の塩業会社に有利に働き、日本の商社は利益を確保できない恐れがあった。
このため、専売局の強い要望もあって「外塩輸入協会」を設立することになり、三井物産、三菱商事、岩井商店、化学塩業、大日本塩業の5社が会合し、各社の買付実績に基づく各塩場の優先順位や各社の取扱数量を決定し昭和13(1938)年2月、同協会が設立された。
これに伴い、輸入塩については「近海塩業会」のメンバーが近海塩を、「外塩輸入協会」のメンバーが遠海塩と準近海塩を取り扱うことになったが、前記のとおり輸入塩の大勢が遠海塩から近海塩に移行していったため、外塩輸入協会は遠海塩の輸入量の激減に伴い活動を休止するに至った。