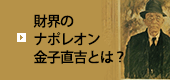羽幌炭砿にまつわる話シリーズ⑯「往時の羽幌炭砿に思いを馳せて(町田叡光)」
社会人としての大半を羽幌炭砿で過ごし、同社の発展に力を尽くす
昭和十五年一月、満三十六歳三ヶ月で渡道することになった。(*)
(*)「回顧録」には渡道に至った経緯が大略次のように記述されており、町田の力量が大いに期待されていたことが窺える。
「神戸製鋼所に勤務していた町田は常務の浅田長平(後・同社社長、会長)から長府工場立上げの責任者に任命され昭和14(1939)年、苦労の末に工場を完成させたがその年の秋、金子直吉と金子三次郎(町田の義兄、後・羽幌炭砿鉄道専務)から北海道に炭鉱を作りに行かないかと誘われた。浅田は猛反対したが、もめにもめた末に金子直吉は当時の神戸製鋼所社長の田宮嘉右衛門に話をつけ、高畑誠一が浅田を説得した結果、町田の北海道行きが決まった」
羽幌に行った最初は太陽産業羽幌砿業所支配人というものだった。最初の仕事は土地の獲得と会社を作ることだ。七月十二日太陽本社が国鉄の大先輩、岡新六氏を社長にして羽幌炭砿鉄道株式会社は発足した。
土地の買収は江野さん、駒井さんのご尽力で順調に進んだ。しかし、御料局からの鉱業用地の借地がなかなかうまく進まない。ある日、訪ねてきた記者に私が「御料局の役人が天皇陛下を傘に着て簡単に許可をくれない」と言ったのをそのまま記事にしたため、旭川御料局の逆鱗にふれたが、何回もお詫びに行って事なきを得た。
その直後、旭川御料局から立花営業課長以下二、三名で山の開発状況を見に来られた。食事の席で談笑しているうちに、同課長に「町田君わからんか」と言われたが何のことかさっぱり分からなかった。「島村だよ」といわれてはっと気がついた。立花課長は島村元帥のご令息で、近藤正太郎塾長(*)の甥に当たられる方で、近藤塾時代に何度かお目にかかったことがあった。築前柳川の立花家に養子に行かれたとのことだった。そんなことから、御料局との関係もスムーズにいくようになった。
(*)町田は神戸高商時代、鈴木商店傘下である「日沙商会の社長、近藤正太郎の私塾「近藤塾」(兵庫県芦屋)に入塾し、そこから高商に通っていた。
鉄道の土木工事は、当時鉄道資材の入手が困難であったにもかかわらず、岡社長のお陰で国鉄から中古品の払下げを受けてなんとか間に合った。工事は(昭和)十五年の雪解けからはじめて十六年の降雪前の完成を予定していたが、十六年の融雪時になって吉野鉄道部長からどうしても出来ない、年内には全長十七粁のうち下の方十一粁が精一杯で、上の六粁は来年の融雪後にとりかかって十月頃完成になると言う。
色々考えた結果、それでは下の十一粁を必ず年内にやってくれ、上の六粁は私が完成すると宣言してしまった。炭鉱夫約三百人を動員し昼夜兼行、夜は投光器とキャップランプをつけ、事務職員も事務を簡素化して勤労奉仕させて、枕木に炭鉱用ライトレールを敷き、炭車で山砂利を散布して道床を作り、下の方十一粁より先に仕上げ、直結して(昭和16年)十二月十二日年完成の運びとなった。吉野鉄道部長の経験と知識を凌駕した苦労と意気込みは今でも語り合うよい思い出である。
剣道の極意「生来の習性を一掃し本来の面目に帰れ」、また白隠禅師が坐禅和讃で「衆生本来仏であるべきものが、生後の風習、教養などに災いされて本来の面目を発揮できず、従に妄想雑念にとらわれていることが多々ある」といった言葉が頭に浮かんだ。
羽幌の炭鉱事業は昭和十五年に始め、約三十年間石炭を掘り続けた。この間、戦時中は戦争遂行にもっとも必要な物資として、戦後約十年間余りは国の経済復興の原動力として、必死の生産をして来たが、昭和三十一年頃から所謂エネルギー革命が起こり、石炭の必要性が急激に減少していき、遂に昭和四十五年末閉山するに至った。
私は学校を出て働いた四十七年間のうち三十七年間、即ち人生の大部分を羽幌炭砿で過ごしたのである。その間楽しいことも苦しいことも数多くあったが、最後の閉山はもっとも苦しいことだった。しかし、戦時中から戦後にかけて国が最も必要とするときに出炭し、殆ど必要性がなくなって止めたのだからたいした悔いはない。
尚、全国の炭鉱が毎年何度となく繰り返していた炭鉱ストだが、私たちの炭鉱だけは終戦後の所謂レッドパージを除いては一度もなく、ストのない炭鉱として全国的に有名になったことは従業員一同とともにいささか誇りとするところである。
羽幌炭砿のほか私が創立した子会社、京北海運、羽幌プロパン石油、大五タクシー、羽幌耐火工業、羽幌運輸、今金鉱山、日高ズンガン、協和石炭、北栄石炭、大五不動産、ミヅチ産業、私が会長または副会長を務めた北海道石炭工業協会、札幌ビルディング協会、北海道事業場健康管理センター、北海道高知県人会、役員をした同交会病院、日本石炭鉱業連合会、北海道鉄道協会、その他関係会社、関係団体などの思い出もつきない。閉山後の整理に五年半かかり、(昭和)五十一年六月、会社末梢登記を完了した。
昨年夏、整理後の山を見に行った。
最早炭鉱も鉄道も建物も壊され、只夏草が生い茂っていた。
松尾芭蕉の "夏草や 兵どもが 夢の跡"
この句がひしひしと胸に迫ってくるのみであった。
(町田叡光の回顧録「八日間のたわ言」(昭和五十四年五月記)より抜粋)