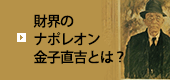羽幌炭砿のあゆみ~Ⅰ.創業前史②~
鈴木商店破綻後、太陽曹達により開発をすすめる
昭和2(1927)年に鈴木商店が破綻した後、金子直吉は鈴木商店の後継会社・太陽曹達でお家再興のプランを練っていた。羽幌炭砿が創立20周年を迎えるに当たり、当時会長であった高畑誠一は、金子直吉の羽幌に対する思いを次のように語っている。
「その後鈴木の整理も曲りなりに大体片付いたので、さすがの金子翁も何か一つまとまった事業を起こして捲土重来せねば主家に対して相済まぬと感じられたのであろう。生来事業が何よりも好きな金子翁であるから種々画策された結果、羽幌炭砿を買いもどして、これで一旗挙げるのが何よりも再興の早道と考えられて太陽鉱工(鉱区を買いとった当時は太陽曹達)が債権銀行から羽幌炭砿の鉱区を買いとり、付近の連続鉱区も順次、新規に入手したのである」(『石炭羽幌』昭和35年7月10号より)
また、城山三郎著の『鼠』では、破綻後、かつての部下が訪ねてきた際に、「『少し金が欲しいのう。10万両ほど欲しい。実は今、考えていることがある。その方面に使いたいんじゃ』と石炭液化の必要性を説き出した。」といった記述があり、羽幌炭砿を軸に石炭液化の量産化を念頭に置いていたと思われる。
石炭液化については、大正期から昭和初期に南満州鉄道(満鉄)にて、基礎研究がおこなわれていた。戦局が拡大していく昭和初期において、石油資源のない日本が生き残るためには石炭から液化燃料を生産することが国益にかなうと金子直吉は考えていたのだろう。なお、日本では結局資材不足から量産化には至らなかったが、ドイツでは軍事用燃料として合成石油の大量生産に成功し、戦闘機用に利用された。
鈴木商店破綻後の羽幌炭砿の各鉱区は台湾銀行と北海道銀行に二分して担保に入っていたが、金子直吉の意志により台湾銀行差入れの10数鉱区は元小樽支店長の志水寅次郎の名義で、残りの北海道銀行差入れ分は直接太陽曹達が買戻し、最終的に全ての鉱区が太陽曹達の所有となった。そして昭和6(1931)年、太陽曹達(後・太陽産業、現・太陽鉱工)は築別、羽幌両地区の炭鉱開発の方針を固め、両地区の実地調査を開始した。
調査を任されたのが後に羽幌炭砿の常務取締役・初代砿業所長となる炭鉱調査のプロフェッショナル、古賀六郎で、昭和10(1935)年には築別地区においてボーリング調査を実施し、地層および炭層の状態を確認した。この調査結果を受け、太陽曹達はこの地区での企業化に目途をつけたのである。